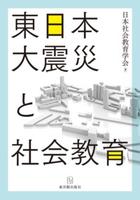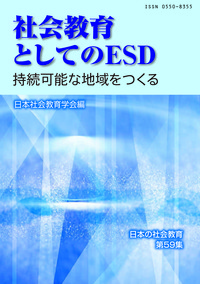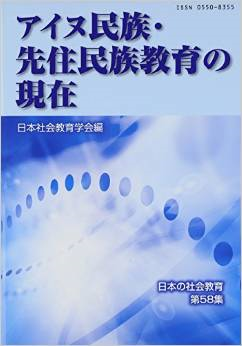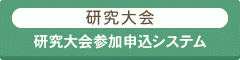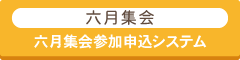日本社会教育学会ジャーナル『社会教育学研究』は、年間2回刊行で、学会員が投稿した論文の掲載(査読あり)、研究大会等の報告、書評や研究動向等を掲載するものです。「会員の自由な投稿、研究交流の場としてフルに活用される」ことを目指して、1964年5月に『日本社会教育学会紀要』の名で刊行されました(古木弘造「刊行のことば」)。その後、2014年に『社会教育学硏究』へと名称変更し、現在に至ります。『社会教育学研究』は、学会員に送付されるほか、一部大学図書館等で閲覧可能です(非売品)。
掲載論文・書評は、J-STAGE(国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営する電子ジャーナルプラットフォーム)で公開しています(第35巻・1999年以降、最新刊まで)。
掲載論文等の情報は、CiNii(国立情報学研究所が提供する学術情報ナビゲーター・サイニー)で検索が可能です。
『社会教育学研究』 第61 巻第2号 目次(最新号)
<<研究論文>>
高坂千夏子 タイにおけるノンフォーマル教育の役割
―山地少数民族対象のコミュニティ学習センターを焦点に―
溝内 亮佑 自主夜間中学の開設過程における支援者の当事者性の獲得
―福岡よみかき教室のボランティアの同和教育運動をめぐる教師経験に注目して―
<<特集論文>> 「社会教育学における余暇・レクリエーションの再検討」
歌川 光一 〈依頼論文〉
社会教育学における「余暇活動の教育・学習としての意味」という間隙とその可能性
杉山昂平・執行治平〈依頼論文〉
趣味に対する社会教育は可能か:趣味の公共的再編成に関する検討
奥村 旅人 高度経済成長期における企業の教育的意図
―『経営者』・『関西経協』の分析を中心として―
横山 詢 社会教育学における「地域」概念の批判的継承
―ポップカルチャーによる感性的つながりの生成を捉えるために―
社会教育士特別プロジェクト中間報告
2025年度六月集会
自主企画助成報告
2023-2024年 社会教育研究の動向
『社会教育学研究』 第61 巻第1号 目次
<<研究論文>>
江口 潔 1930年代後半から1940年代初頭の商店街における店員指導事業
―北沢通商店街商業組合の店員道場を中心に―
小野瀬 剛志 グローバリゼーションは「外部のない時代」か
―「社会」変革のための教育から「資本主義」の変革のための教育へ―
永田 誠 <子育て>における親の「学び」に関する質的考察
―こども園保護者懇談会の2年間にわたる記録から―
王 倩然 デスカフェに関する国際的研究動向
―生涯学習の視点によるデスエデュケーションの研究の可能性―
村瀬 桃子 共同的な学習による包括的性教育の萌芽
―1990年代の愛知“人間と性”教育研究協議会の活動を手がかりに―
『社会教育学研究』 第60巻第2号 目次
<<研究論文>>
杉山 昂平, 矢作 優知, 横田 伸治, 山内 祐平
ユースセンターを利用する青少年と地域の大人を仲介するドロップイン・プログラムの
デザインに関する実践的検討
松岡 悠和 教化動員期の地方社会教育行政
―滋賀県における社会教育委員制度の成立過程を中心に―
水野 聖良 「Space」と「Bridge」の形成を目指した関係性構築
―ユースセンターで実践される工夫としての趣味嗜好の活用―
執行 治平, 大津 恵実, 寺田 純子 青少年の育ちを支える「居場所づくりの方法論」の解明にむけて
―日常の関わりに対する会話分析的な観察から―
堀 薫夫 生成期におけるマルカム・ノールズの成人教育論
横山 詢 盆栽雑誌の記述に現れる山名次郎の思想
―最初期社会教育論の再検討に向けて―
<<特集論文>> 「障害をめぐる社会教育・生涯学習」
津田 英二 障害の問題は社会教育研究と実践に何を問いかけているか
池田 法子 手話サークルにおける市民の学習過程
―交流から生じる葛藤や認識の変容に着目して―
鈴木 菖 福祉事業型専攻科に通う知的障害のある青年が抱える困難と支援の特徴
―Y専攻科でのフィールド調査を通して―
橋田 慈子 命の選別の問題を提起する障害当事者・家族の運動と社会の人々の学び
―イギリスの「Don’t Screen Us Out!」の実践に着目して―
土畠 智幸 みらいつくり大学
―障害当事者と医療者でつくる社会教育の場―
『社会教育学研究』 第60巻第1号 目次
≪研究論文≫
伊藤 史彦 大正期における学校と地域社会の関係
―名古屋市の「連区教育会」を例に―
木下 卓弥 医療労働者の学習の組織化と協同の生成の展開
―1970年代の長野県厚生連佐久総合病院小諸分院の労働組合に着目して―
鈴木 理仁 芸術家による学習支援のための専門性
―アートワークショップにおける権威性に着目して―
村上 竜雄 内発的発展論における「キー・パースン(key-person)」概念の再検討
―地域づくり主体としての学びに着目した考察
2023年度六月集会
第70回研究大会
第14回日韓学術交流研究大会報告
倫理委員会報告
社会教育士特別プロジェクト報告
若手会員の萌芽的研究及び研究交流の奨励に関する助成報告
書評・図書紹介
2023年度 日本社会教育学会のあゆみ
『社会教育学硏究』第59巻 目次(2023/06)
《研究論文》
岡 幸江 「非合理性」の観点に基づく社会教育の主体理解の検討
―伝承者阿部ヤヱと歌人阿部八重をめぐって―
小川 史 占領下の憲法普及劇―検閲台本から見るその性格―
農中 至・山城千秋 祖国復帰運動における青年団運動の再検討―奄美・沖縄の固有性に注目して―
松岡 悠和 少年団日本連盟と宗教系少年団の関係―金光教・本願寺派・大谷派を中心に―
山梨 あや 疎開者による「地域」の発見
― 疎開生活における学校・家庭・地域の連絡・協力関係 ―
2022年度六月集会
第69回研究大会
第13回日韓学術交流研究大会報告
第7回ユネスコ国際成人教育会議報告
年報紹介
倫理委員会報告
若手会員の萌芽的研究及び研究交流の奨励に関する助成報告
書評・図書紹介
2022年社会教育学会会員・発表論文一覧
2022年度 日本社会教育学会のあゆみ
『社会教育学硏究』第58巻 目次(2022/06)
《論文》
亀口 まか 女性労働と児童保護の視点からみる1944年保護者不在家庭児童調査の
成立過程
瀬戸 麗 外国にルーツをもつ子どもの学習保障にむけた学校と地域組織の連携
― 権力関係を前提としない連携の構築に着目して―
永瀬 悦子 山間豪雪地帯の出産に関わる開業助産師の活動展開過程と学習過程
―福島県南会津「田島町」を事例に―
堀本 暁洋 高度成長期における大規模社会教育施設の計画と地域文化活動の関わり
―川崎市産業文化会館に着目して―
2021年度六月集会
第68回研究大会
第12回日韓学術交流研究大会報告
年報紹介
倫理委員会報告
若手会員の萌芽的研究及び研究交流の奨励に関する助成報告
書評・図書紹介
2021年社会教育研究の動向
2021年度 日本社会教育学会のあゆみ
『社会教育学硏究』第57号 目次(2021/06)
《論文》
木下 卓弥 階層分化を超えた地域自治への学習組織化の過程の解明
-60年代の長野県栄村の学習運動に着目して-
徐 真真 明治後期における家庭雑誌文化の創出と読者の役割
-『家庭之友』の読者層と誌面上における交流に着目して-
中山 博晶 寄せ場・釜ヶ崎における生活経験の再構成
-地域の表現活動に参加する当事者の語りに着目して-
プロジェクト研究活動報告
第67回研究大会
年報紹介
若手会員の萌芽的研究及び研究交流の奨励に関する助成報告
書評・図書紹介
2020年社会教育研究の動向
新型コロナウイルス感染症拡大に対する本学会の対応
2020年度 日本社会教育学会のあゆみ



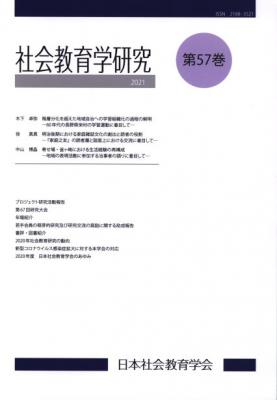
 現代社会教育学事典
現代社会教育学事典 SDGsと社会教育・生涯学習
SDGsと社会教育・生涯学習 高齢社会と社会教育
高齢社会と社会教育 ワークライフバランス時代の社会教育
ワークライフバランス時代の社会教育