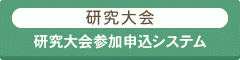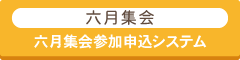プロジェクト研究「男女平等・ジェンダー公正をめぐる課題と社会教育の可能性」公開研究会のご案内
【公開研究会のご案内】『つくられる〈農村女性〉:戦後日本の農村女性政策とエンパワーメントの物語』をめぐって
『つくられる〈農村女性〉:戦後日本の農村女性政策とエンパワーメントの物語』(岩島史、有志舎、2020年)の内容をレビューした上で、その内容について社会教育の視点からコメント・意見交換を行います。(主旨は末尾を参照してください)
○日時:2025年11月21日(金)18時30分~21時(オンライン)
○報告者:千葉悦子さん(福島大学名誉教授)、木下卓弥さん(石巻専修大学)
○企画:プロジェクト研究「男女平等・ジェンダー公正をめぐる課題と社会教育の可能性」
(辻智子・北海道大学、tsujitomoko@edu.hokudai.ac.jp)
○参加申込:tominagatakahiro@gmail.com(冨永貴公(都留文科大学)まで)
※開催日の数日前にオンラインのアドレスをお送りします。
○主旨
3年目に入ったプロジェクト研究「男女平等・ジェンダー公正をめぐる課題と社会教育の可能性」では、地域社会の意思決定過程や自治の場におけるジェンダー公正とそれに伴って生じる諸変化をとらえそこでの学習の可能性を探ることを課題に設定している。年報『ジェンダーと社会教育』(2001年)が残した研究課題として「農村」「農業」「地方」の視点を確認した私たちは2024年六月集会で次の問題提起を行った。
「農業分野では女性農業者への政策が進んだ。生活改善普及事業の縮小に対し、女性農業者個人のネットワーク化への動きを政策が後押しするようになった。職業として農業を選択する若手女性の増加が課題とされ、「農業女子プロジェクト」など2010年代以降の農業政策は個別化する女性農業者の課題解決や自己実現に寄与するものと評価されている。その一方で、「女性らしさ」の強調による性別役割の固定化、プロジェクトに参加が困難な「嫁」と活動する「若い女性」の二分化および「農業女子=若い女性」という印象の助長などの問題も指摘されている」。
こうした状況の中で社会教育実践および研究の可能性を探る議論の端緒として本研究会を企画した。ここで取り上げる書籍は、農業経済学の視点から、社会教育や生活改良普及事業の文脈における「エンパワーメント」の「物語」を批判的に論じるものである。こうした見解をどのように受けとめるのか、どのように応答するのか、それを考えることで社会教育の可能性を考える機会としたい。
<事務局員の勤務について>
事務局は事務局は事務局は祝祭日を除く(月)・(木) 10:00~16:00 リモートワークのため、電話受付はしておりません。お問合せ等はメールにてご連絡ください。
【事務局メール: jssace.office@gmail.com】
ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【会費振込先】今年度(2026年度)が2025年9月から始まっています。会費納入状況は各自個人画面で確認の上、会費未納分と今年度分の会費の振込みをお願いいたします。尚、2026年度会費減額申請は受付終了しています。2027年度については2026年7/1(水)~2027年8/15(土)です。減額希望の会員は期間内に<会費減額申請システム>から申請し、承認の連絡が来次第、会費の納入をしてください。(10月開催予定の理事会で承認後ご連絡いたします。)
ゆうちょ銀行 振替口座 00150-1-87773
他金融機関からの振込用口座番号:〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座0087773
*口座振替ご希望の方 個人ページにアクセスした後、下方<会則・文書等>にあります「預金口座振替依頼書」に必要事項を入力後プリントアウトし、押印したものを学会事務局までご郵送ください。今年度(2026年度)は2025年10月15日必着で〆切りました。
*領収書が必要な方 会費等の領収書が必要な方は、メールにて領収書の宛名・送付先をお知らせください。
◎会員の方は各自、登録メールアドレスの確認をお願いいたします。
「六月集会プログラム」「学会からのお知らせ」「研究大会プログラム」はネット配信のみになります。
〒189-0012
東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail:jssace.office◎gmail.com
(◎を@に変えてください)
(祝祭日除く月・木曜日 10:30-16:30 リモートワーク中)
Tel:090-5782-1848 ※現在電話受付停止中