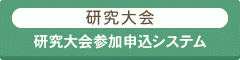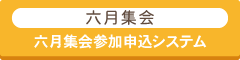最新情報
『社会教育学研究』第62巻第1号における論文電子投稿システム稼働のお知らせ
日本社会教育学会 会員各位
『社会教育学研究』第62巻第1号(2026年5月刊行予定)における論文電子投稿システムを稼働致しました。
論文投稿を検討されている方は、下記の要項をよく読んだ上で、学会HPにログインし、画面左の列の茶色のボタン(社会教育学研究論文投稿システム)から入ってください。ページの下部に投稿フォームがありますので、必要事項を記入の上、投稿するようにして下さい。
【投稿原稿受付期間】
2025年11月1日(土)~2025 年11月30日(日)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、年間2回の刊行です。今回は、第1号の募集で【一般論文】を受け付けます(第2号の募集は、2026年5月1日〜5月31日を予定)。
【原稿種別について】
・『社会教育学研究』では「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
・なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
【査読基準の公開】
・『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の留意点】
・本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。所属機関に研究倫理審査規程がある場合は、必ず所属機関の規程に従ってください。また、所属機関の研究倫理審査を経ている場合は、その旨を本文中に記載ください。
・また、投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。特に連続投稿(投稿規程の3)、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
・近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
口座引き落としに関して
日本社会教育学会 各位
これまで口座振替の場合は希望者に書類を郵送して、必要事項を記入後押印して返送してもらっておりましたが、今年から電子ファイル版の提供が開始されました。
つきましては、会費の引落口座を変更・新規ご希望の方は、下記の通り、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
①学会事務局にメールを入れる
②学会HPにログインをする
③個人会員ページ内、左列「会則・文章等」の中の最下部のファイル(預金口座振替依頼書)を各自ダウンロードし必要事項記載後プリントアウトして押印したものを学会事務局宛に郵送する
上記を含め、引落し口座の変更・取止め、または新規ご希望の方の受付については、2025年9月末日までに事務局宛ご連絡頂くように通信にて告知しておりましたが、こちらを10月15日締め切りに延長を致します。
なお、次回2026年度分引落は、2025年12月20日(予定)ですので、各自、残高をご確認ください。以上、宜しくお願いします。
日本社会教育学会 事務局
『社会教育学研究』第62巻第1号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第62巻第1号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第62巻第1号(2026年6月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。
投稿にあたっては、『社会教育学研究』第61巻1号末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】2025年11月1日(土)~2025年11月30日(日)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、年間2回の刊行です。今回は、第1号の募集で【一般論文】を受け付けます(第2号の募集は、2026年5月1日〜5月31日を予定)。
【原稿種別について】
l 『社会教育学研究』では、「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
l 研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
l なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
【査読基準の公開】
『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の注意点】
l 本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。なお、倫理的配慮が必要な内容であり、所属機関で倫理研究審査を受けている場合は、その旨を本文中に示していただくようにお願いいたします。
l 投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。前号に採用された者の連続投稿はできませんが、特集テーマに関する論文等はこの限りではありません(投稿規程の3)。また、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)、重複投稿(各号で投稿できるのは単著、共著問わず1人1本です)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
l 近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
2026年度会費減額申請システムの稼働について
日本社会教育学会 会員各位
2026年度(2025年9月~2026年8月まで)の「会費減額制度」の申請を受け付けます。本制度のご利用を希望される会員は、下記の要領にてフォームより申請してください。以前に「減額」を継続と申請された方はあらためて申請する必要はございません。
【対象】
・学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等(※本制度概要4参照)
【申請期間】
・2025年7月1日(火)~2025年8月15日(金)
【申請方法】
・下記フォームより申請
《会費減額制度の概要》
1.本制度は、経済的な制約により学会加入が困難になる状況を少しでも改善することを目的として、個人への経済支援を行うものである。
2.本学会は、本人からの申請にもとづき年会費の減額を行う。
3.一年を単位として、年会費1万円を6,000円とする(4,000円の減額)。
4.申請者は、会費を払う年度において、大学院生または常勤職にない会員等とする。本制度の主旨に則り、学術振興会の特別研究員、および、それに準ずる身分の者等、一定金額の収入のある者は申請できない。なお、申請者は、減額を受けようとする年度の前年度までの会費滞納のないことを要する(新規の入会者を除く)。
5.申請者は、学会HPの個人ページにある<会費減額申請システム>から申し込む。
6.申請受付期間は、毎年7月1日〜8月15日とする(期限厳守)。新入会者で減額希望の場合は入会届とともに減額申請書に必要事項を記入し提出することができる。(減額申請書を提出する場合は、会費の振込は6,000円とする。)
7.本学会は、新年度開始後の理事会(10月開催予定)において、申請者リストを回覧し、承認を行う。その後、事務局より承認の可否をメールにて申請者に通知する。
8.申請者は、申請の承認可否の結果を受けた後に当該年度の年会費を支払うものとする。
9.減額制度は一年ごとに適用する。申請は年度ごとに受けつける。但し、継続申請した場合を除く。継続確認は事務局までお問合せください。
2026-2027年度 理事選挙インターネット投票開始のお知らせ
日本社会教育学会会員各位
2026-2027年度理事選挙のインターネット投票を開始しました。
インターネット投票は、短時間で簡単に投票することができます。
多くの皆様にご投票いただき、投票率向上にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
《投票期間》
6月25日(水)から7月25日(金)まで
《投票方法》
学会ホームページ内の「理事選挙投票ページ」から投票してください。詳しい投票方法は「理事選挙投票ページ」に記載されています。
《理事選挙投票ページへのアクセス方法》
①学会ホームページにログインし、「個人会員ページ」に入ってください。
②サイドメニュー(スマートフォンの場合はページ下部のメニュー)の「個人会員ページ」の下に表示される「理事選挙投票ページ」からアクセスしてください。
《注意事項》
・「理事選挙投票ページ」からダウンロードできる「選挙のしおり」を必ずお読みください。
・「選挙のしおり」に記載されているご自身の所属ブロックをご確認ください。
・郵送での投票を希望された会員は「理事選挙投票ページ」にアクセスできません。別途、郵送にてご連絡差し上げます。
《問い合わせ》
インターネット投票についてご不明な点等がございましたら、学会事務局(jssace.office@gmail.com)までお問い合わせください。
学会声明「日本学術会議法案に反対する」
2025年6月7日に開催された日本社会教育学会第1回全国理事会の議を経て、以下の声明を発出します。
日本学術会議法案に反対する
2025年6月7日
日本社会教育学会
日本社会教育学会は、2025年4月29日に「日本学術会議法案に反対し、同法案の抜本的修正を求める日本学術会議第194回総会の決議を支持する」という常任理事会声明を発出した。
その後、5月9日に担当相から「特定のイデオロギーとか党派的な発言を繰り返す会員は、この法案のなかで今度は学術会議が解任ができる」との発言があり、また「不透明な資金提供を受けるなど公正性に問題があるような人物がまず会員にならないよう適切に対応されるものと考えております」との言及もあった。本学会は、学術研究団体としてこの発言を容認することはできない。
それは第一に、学術会議の自治に関する事柄について、担当相が内容に踏み込みつつ排除・解任基準を示したことは、学問の自由が要請する高度な自治の世界に外部から学術以外の評価尺度を持ち込むことを意味するからである。
第二に、学術会議を含む学術研究団体は、研究倫理の遵守を前提としつつ客観的な事実に基づく学術的達成を尺度として研究を評価するのであり、イデオロギーやオピニオンを評価基準とすることはないからである。それにもかかわらず、このような解任要件を示すことは、日本学術会議法案が、科学的研究の成果を特定のイデオロギーに基づくと断じ当該研究者を排除する可能性を開くことを意味する。
第三に、「特定のイデオロギー」は曖昧な概念であり、また「公正性」についても拡大解釈が可能な表現となっているからである。その意味するところを明確にしなければ、厳密な議論は成立しない。しかるに2020年10月1日に任命されなかった6名の任命拒否理由が明らかにされていないため、それらの研究者の政府・政策の批判を「特定のイデオロギー」に基づく活動と評して排除したとの疑念は未だに払拭できない。この疑念の払拭は審議の前提である。したがって現状では日本学術会議法案についても、そのような不当な解釈・評価に基づく運用が想定されていると推測せざるを得ない。
以上の理由に基づき、本学会は学問の自由を守る立場から、引き続き日本学術会議法案に反対する。
以上
『社会教育学研究』第61巻第2号における論文電子投稿システム稼働のお知らせ
日本社会教育学会 会員各位
『社会教育学研究』第61巻第2号(2025年11月刊行予定)における論文電子投稿システムを稼働致しました。
論文投稿を検討されている方は、下記の要項をよく読んだ上で、学会HPにログインし、画面左の列の茶色のボタン(社会教育学研究論文投稿システム)から入ってください。ページの下部に投稿フォームがありますので、必要事項を記入の上、投稿するようにして下さい。
【投稿原稿受付期間】
2025年5月1日(木)~2025 年5月31日(土)
【原稿種別について】
<一般>(自由テーマによる論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・ 研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
・なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
<特集>(以下の特集テーマに基づいた論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・テーマ:余暇・レクリエーションを通じた社会教育学の再検討
・趣旨: 地域住民のウェルビーイング向上や生きがいづくりを促す活動の一つとして、いわゆる余暇・レクリエーションが存在する。本特集では、余暇・レクリエーションの形成的側面に着目し、以下のような趣旨の論考を広く募集する。
第一に、社会教育における余暇・レクリエーションの位置づけをめぐる成果や課題について募集する。従来の社会教育学研究では中心的な検討対象として論じられてこなかった、地域の文化活動、スポーツ活動、生活文化を通じたノンフォーマル教育・学習(保育や学校教育との連携を含む)、もしくは家庭や個人の趣味活動やメディア接触といったインフォーマル教育・学習を取り上げ、「楽しむ」「遊ぶ」を主目的とする実践や議論を社会教育学研究と架橋していく論考を想定する。
第二に、余暇・レクリエーションの検討を通じて明らかとなる「社会教育学」の枠組みをめぐる課題についてである。例えば、自己教育概念の再検討(教育学における教養論・修養論との異同)、文化社会学の進展を背景に据えた社会教育学における大衆文化観・消費文化観・メディア観等の更新、余暇・レクリエーションを通した社会教育学と教育学の関係の再考、生涯学習論や成人教育学と学習科学の関係等がテーマとして挙げられる。
【査読基準の公開】
・『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の留意点】
・ 本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。所属機関に研究倫理審査規程がある場合は、必ず所属機関の規程に従ってください。また、所属機関の研究倫理審査を経ている場合は、その旨を本文中に記載ください。
・また、投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。特に連続投稿(投稿規程の3)、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
・近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
日本学術会議法案に関する声明
<日本学術会議法案に関する声明>
日本学術会議法案に反対し、同法案の抜本的修正を求める日本学術会議第194回総会の決議を支持する。
2025年4月29日 日本社会教育学会常任理事会
『現代社会教育学事典』の正誤表
『社会教育学研究』第61巻第2号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第61巻第2号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第61巻第2号(2025年11月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。投稿にあたっては、『社会教育学研究』第60-2巻末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】
2025年5月1日(木)~2025 年5月31日(土)
【原稿種別について】
<一般>(自由テーマによる論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・ 研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
・なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
<特集>(以下の特集テーマに基づいた論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・テーマ:余暇・レクリエーションを通じた社会教育学の再検討
・趣旨: 地域住民のウェルビーイング向上や生きがづくりを促す活動の一つとして、いわゆる余暇・レクリエーションが存在する。本特集では、余暇・レクリエーションの形成的側面に着目し、以下のような趣旨の論考を広く募集する。
第一に、社会教育における余暇・レクリエーションの位置づけをめぐる成果や課題について募集する。従来の社会教育学研究では中心的な検討対象として論じられてこなかった、地域の文化活動、スポーツ活動、生活文化を通じたノンフォーマル教育・学習(保育や学校教育との連携を含む)、もしくは家庭や個人の趣味活動やメディア接触といったインフォーマル教育・学習を取り上げ、「楽しむ」「遊ぶ」を主目的とする実践や議論を社会教育学研究と架橋していく論考を想定する。
第二に、余暇・レクリエーションの検討を通じて明らかとなる「社会教育学」の枠組みをめぐる課題についてである。例えば、自己教育概念の再検討(教育学における教養論・修養論との異同)、文化社会学の進展を背景に据えた社会教育学における大衆文化観・消費文化観・メディア観等の更新、余暇・レクリエーションを通した社会教育学と教育学の関係の再考、生涯学習論や成人教育学と学習科学の関係等がテーマとして挙げられる。
【査読基準の公開】
・『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の留意点】
・ 本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。所属機関に研究倫理審査規程がある場合は、必ず所属機関の規程に従ってください。また、所属機関の研究倫理審査を経ている場合は、その旨を本文中に記載ください。
・また、投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。特に連続投稿(投稿規程の3)、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
・近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
「学会からのお知らせ2024年第3号(通号242号」について お詫びと修正について
「学会からのお知らせ2024年第3号(通号242号」について
お詫びと修正について
先般発行した表記「学会からのお知らせ」に掲載したラウンドテーブル:「社会教育士のスキルの尺度の開発について」報告において、著者校正前の原稿が掲載されたという誤りがありました。
ここに担当理事として執筆者並びに会員の皆さまにお詫びし、修正させていただきます。なお、修正に関しましては、該当原稿を正しく差し替えしも添付のとおりの「学会からのお知らせ2024年第3号(通号242号)」といたします。
担当理事 村田和子、前田耕司
『社会教育学研究』論文電子投稿システムの稼働について
日本社会教育学会 会員各位
2024年11月1日(金)0:00~11月30日(土)23:59までの期間にて、『社会教育学研究』第61巻第1号(2025年6月刊行予定)における論文電子投稿システムを稼働致します。
論文投稿を検討されている方は、下記の要項をよく読んだ上で、学会HPにログインし、画面左の列の茶色のボタン(社会教育学研究論文投稿システム)から入ってください。投稿フォームがありますので、必要事項を記入の上、投稿するようにして下さい。
事務局
****
『社会教育学研究』第61巻第1号への投稿原稿の募集(再掲)
『社会教育学研究』第61巻第1号(2025年6月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。
投稿にあたっては、『社会教育学研究』第60巻1号末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】
2024年11月1日(金)~2024年11月30日(土)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、第60巻より年間2回の刊行となりました。今回は、第1号の募集で【一般論文】を受け付けます(第2号の募集は、2025年5月1日〜5月31日を予定)。
【原稿種別について】
『社会教育学研究』では、「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
【査読基準の公開】
『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の注意点】
本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。なお、倫理的配慮が必要な内容であり、所属機関で倫理研究審査を受けている場合は、その旨を本文中に示していただくようにお願いいたします。
投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。前号に採用された者の連続投稿はできませんが、特集テーマに関する論文等はこの限りではありません(投稿規程の3)。また、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)、重複投稿(各号で投稿できるのは単著、共著問わず1人1本です)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
『社会教育学研究』第61巻第1号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第61巻第1号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第61巻第1号(2025年6月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。
投稿にあたっては、『社会教育学研究』第60巻1号末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】
2024年11月1日(金)~2024年11月30日(土)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、第60巻より年間2回の刊行となりました。今回は、第1号の募集で【一般論文】を受け付けます(第2号の募集は、2025年5月1日〜5月31日を予定)。
【原稿種別について】
『社会教育学研究』では、「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
【査読基準の公開】
『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の注意点】
本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。なお、倫理的配慮が必要な内容であり、所属機関で倫理研究審査を受けている場合は、その旨を本文中に示していただくようにお願いいたします。
投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。前号に採用された者の連続投稿はできませんが、特集テーマに関する論文等はこの限りではありません(投稿規程の3)。また、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)、重複投稿(各号で投稿できるのは単著、共著問わず1人1本です)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
「第15回日韓学術交流研究大会開催概要」と「参加申込方法」のお知らせ (二次案内)
日本社会教育学会 関係各位
第15回日韓学術交流研究大会概要 <二次案内>
第15回日韓学術交流研究大会について開催概要が決まりましたので、以下の通り、お知らせいたします。今回は、両国の重要課題である「社会学習空間と生涯学習(Social Learning Spaces and Lifelong Learning)」をテーマに、日韓の研究者、実践者が集い、実りある議論ができることを目指します。
多くの皆様の参加をお待ちしております。
なお、本件詳細は、第15回日韓学術交流研究大会開催概要(2次案内).pdfも併せて、ご参照下さい。
1. 日時:2024年10月25日(金)~26日(土) *25日はエクスカーション
2.開催方法:対面・オンライン併用(ハイフレックス方式)
3.開催場所:韓国・水原華城(スウォンファソン)博物館
住所:21 Changnyong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea(京畿道 水原市 八達区 蒼龍大路21)(Googlemap) TEL. +82-31-228-4242
4. テーマ:「社会学習空間と生涯学習(Social Learning Spaces and Lifelong Learning)」
5.共催:日本社会教育学会・韓国平生教育学会
6.参加費:
・現地参加の場合:
一般会員:50,000ウォン(約5,300円)、学生・大学院生:25,000ウォン(約2,600円〉
(参加費には、大会資料集の代金、26日のお昼と懇親会費などが含まれます。渡航費及び宿泊代は各自負担。)
・オンライン参加の場合:無料
7. スケジュール: (両日とも終了後懇親会があります。)
【1日目】エクスカーション 「歴史社会的空間としての華城」
・日時: 2024年10月25日(金) 16:00-18:00
・講師: ハン・ドンミン(水原華城博物館館長)
・集合場所:後日、現地参加者に別途ご連絡いたします。
・コース: 八達山→旧富国園→記憶の部屋(水原家族女性会館別館)→華城行宮周辺
日帝強占期に水原中心部にあった八達山(パルタルサン)の頂上に神社を建て、華城行宮を近代化するという名の下で無くし、病院や警察署等を建てた。その後、1997年に華城が世界文化遺産に登録され、「華城城役儀軌」(朝鮮後期華城の城郭築造に関する経緯と制度、意識等を収録した本、1801年発行)に基づいて復元された。その時、そこに住んでいた住民たちから反発があったが、住民たちと話し合い、復元する過程において芸術をマウル(地域)共同体として活用。以後芸術と環境というコンテンツで「華城行宮マウルづくり」を進めてきている。一方、商業化によるジェントリフィケーション問題が起こり、華城行宮周辺に住む住民たちの共同体に対する悩みや活動が行われ続けている。
【2日目】日韓学術交流研究大会プログラム
・2024年10月26日(土)9:00-18:00
・会場:水原華城博物館(オンライン配信併用)
| 時間 | 報告テーマ | 報告者 |
| 9:00- | 受付 | |
| 9:20- | 開会 | |
| 両学会長の挨拶 | 梁炳賛(ヤンビョンチャン)(韓国平生教育学会会長・公州大学) | |
| 宮崎隆志(日本社会教育学会会長・北海道文教大学) | ||
| 9:40- | デジタル・ポストニューマン時代における文化学習生態系−空間・人・教育のつながり | 梁恩娥(ヤンウナ)(ナザレ大学) |
| 10:20- | 日本における「社会学習空間」の拡張と社会教育施設・文化施設関連法制の展開 |
栗山究(法政大学非常勤講師) |
| 11:00- | 討論 | |
| 11:40- | 文化活動における平生学習−文化学習環境の構造 | 張智恩(チャンジウン)(成均館大学) |
| 12:00- | 昼食 | |
| 13:30- | 日本の先住民族アイヌの現状と課題−博物館活動を中心として | 若園雄志郎(宇都宮大学) |
| 14:10- | 討論 | |
| 14:30- | 休憩 | |
| 15:10- | 地域住民施設の複合空間化と平生教育(仮) | 朴志淑(パクジスク)(慶一大学) |
| 15:50- | 社会教育施設は社会的な課題にどう向き合うか | 新藤浩伸(東京大学) |
| 16:30- | 平和の少女像−記憶・運動・連帯の空間化 | 鄭賢卿(チョンヒョンギョン)(慶熙大学) |
| 17:10- | アートにおける女性たち | 矢内琴江(長崎大学) |
| 17:30- | 討論 | |
| 17:50- | 閉会 | |
8. 参加申込方法:下記、グーグルフォームからのお申し込みとなります。申込締切は、現地参加の場合は、10月6日(日)、オンライン参加は申込締切が、10月18日(金)となりますのでご注意ください。 →(申込URL) https://forms.gle/pwLrwsUVrxKTNNYJ8
*現地参加申込の方は、各自航空券と宿泊先の予約を行ってください。
9. 情報提供(宿泊先について):
・以下、会場近辺のホテルを参考までにお知らせします。
【水原駅の近辺】※博物館まではバスまたはタクシーでの移動になります。博物館のすぐ前にバス停があります。
①S Stay Hotel (Googlemap) おすすめ!
交通:博物館まで20分(バスで15分、徒歩5分)博物館のすぐ前のバス停で下車。タクシーで10分(料金は800円程度)
予約情報: https://www.booking.com/hotel/kr/eseuseuteihotel.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊7千円~1万円弱。(予約時期のよって異なる)
② HOTEL MYEONG JAK (Googlemapリンク)
交通: 博物館まで20分(バスで15分、徒歩5分)博物館のすぐ前のバス停で下車。タクシーで10分(料金は800円程度)
予約情報: https://www.booking.com/hotel/kr/myeong-jak.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊7千円~1万円弱。(予約時期のよって異なる)
【水原華城の近辺】※博物館まで徒歩で移動できます。
①Suwon Dono1796 Hotel (Googlemap: https://maps.app.goo.gl/2ZU1DsiseyqqULyG6)
予約情報:https://www.booking.com/hotel/kr/dono.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊9千円程度
②ファソン ゲストハウス(Hwaseong Guesthouse)(Googlemap)
予約情報:https://www.booking.com/hotel/kr/hwaseong-guesthouse.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊7千円~1万円弱。
博物館まで徒歩で10分ですが、ゲストハウスなので施設面ではホテルほどきれいではありません。
【その他】値段高めのホテル
①ラマダ プラザ スウォン Googlemap
交通:博物館まで20分(バスで10分、徒歩10分)タクシーで8分(料金は800円程度)
予約情報:https://www.booking.com/hotel/kr/ramada-plaza-suwon.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊2万円弱。
②イビス アンバサダー スウォン(Ibis Ambassador Suwon)(Googlemap)
予約情報: https://www.booking.com/hotel/kr/ibis-suwon-ambassador.ja.html
交通:博物館まで交通手段で30分(バス20分、徒歩15分)乗り換えがあるので、移動は不便なほうです。タクシーで12分(料金は1000円程度)
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊1万5千円弱。
10. 本件担当:
国際交流担当理事 李正連(東京大学)・呉世蓮(関東学院大学)
国際交流担当幹事 金亨善(東北大学)
「第15回日韓学術交流研究大会開催概要」と「参加申込方法」のお知らせ
日本社会教育学会 関係各位
第15回日韓学術交流研究大会概要 <一次案内>
第15回日韓学術交流研究大会について開催概要が決まりましたので、以下の通り、お知らせいたします。今回は、両国の重要課題である「社会学習空間と生涯学習(Social Learning Spaces and Lifelong Learning)」をテーマに、日韓の研究者、実践者が集い、実りある議論ができることを目指します。
多くの皆様の参加をお待ちしております。
1. 日 時:2024年10月25日(金)~26日(土)*25日はエクスカーション
2.開催方法:対面・オンライン併用(ハイフレックス方式)
3.開催場所:韓国・水原華城博物館
住所:21 Changnyong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea(京畿道 水原市 八達区 蒼龍大路21)(Googlemap) TEL. +82-31-228-4242
4. テーマ:「社会学習空間と生涯学習(Social Learning Spaces and Lifelong Learning)」
5.共催:日本社会教育学会・韓国平生教育学会
6.参加費:
・現地参加の場合: 5万ウォン(約5,500円)(参加費には、大会資料集の代金、26日のお昼と懇親会費が含まれます)、渡航費及び宿泊代は各自負担。
・オンライン参加の場合:無料
7. スケジュール:
◇10月25日(金) 14時以降:エクスカーション
・韓国京畿道水原市にある「華城」は、朝鮮王朝第22代正祖太王が1790年代に建設したお城で、1997年にユネスコ文化遺産に登録されている。(詳しくは、日本語版ホームページ(http://www.swcf.or.kr/japan/?p=31)をご参照ください。)
・この地にあった植民地時代の神社や学校、病院などの施設に関する歴史や、全国では市民たちの力で初めて建てられた慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」、そして水原華城博物館などを歩き回りながら、歴史の中で施設や空間がどう変わってきたのかを見学する予定。
◇10月26日(土) 会場:水原華城博物館 :研究大会
・詳細なプログラムは、後日ご案内します。
8. 参加申込方法:下記、グーグルフォームからのお申し込みとなります。申込締切は、現地参加の場合は、10月6日(日)、オンライン参加は申込締切が、10月18日(金)となりますのでご注意ください。
https://forms.gle/pwLrwsUVrxKTNNYJ8
9. 情報提供(宿泊先について):
・以下、会場近辺のホテルを参考までにお知らせします。
【水原駅の近辺】※博物館まではバスまたはタクシーでの移動になります。博物館のすぐ前にバス停があります。
①S Stay Hotel (Googlemap)
交通:博物館まで20分(バスで15分、徒歩5分)博物館のすぐ前のバス停で下車。タクシーで10分(料金は800円程度)
予約情報: https://www.booking.com/hotel/kr/eseuseuteihotel.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊7千円~1万円弱。(予約時期のよって異なる)
② HOTEL MYEONG JAK (Googlemapリンク)
交通: 博物館まで20分(バスで15分、徒歩5分)博物館のすぐ前のバス停で下車。タクシーで10分(料金は800円程度)
予約情報: https://www.booking.com/hotel/kr/myeong-jak.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊7千円~1万円弱。(予約時期のよって異なる)
【水原華城の近辺】※博物館まで徒歩で移動できます。
①Suwon Dono1796 Hotel (Googlemap: https://maps.app.goo.gl/2ZU1DsiseyqqULyG6)
予約情報:https://www.booking.com/hotel/kr/dono.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊9千円程度
②ファソン ゲストハウス(Hwaseong Guesthouse)(Googlemap)
予約情報:https://www.booking.com/hotel/kr/hwaseong-guesthouse.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊7千円~1万円弱。
博物館まで徒歩で10分ですが、ゲストハウスなので施設面ではホテルほどきれいではありません。
【その他】値段高めのホテル
①ラマダ プラザ スウォン Googlemap
交通:博物館まで20分(バスで10分、徒歩10分)タクシーで8分(料金は800円程度)
予約情報:https://www.booking.com/hotel/kr/ramada-plaza-suwon.ja.html
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊2万円弱。
②イビス アンバサダー スウォン(Ibis Ambassador Suwon)(Googlemap)
予約情報: https://www.booking.com/hotel/kr/ibis-suwon-ambassador.ja.html
交通:博物館まで交通手段で30分(バス20分、徒歩15分)乗り換えがあるので、移動は不便なほうです。タクシーで12分(料金は1000円程度)
Agoda/Booking.com等の予約サイトで一泊1万5千円弱。
10. 本件担当:
国際交流担当理事 李正連(東京大学)・呉世蓮(関東学院大学)
国際交流担当幹事 金亨善(東北大学)
※詳細は下記PDFを参照
第15回日韓学術交流研究大会開催概要(1次案内).pdf
2025年度「会費減額制度申請申込」の受け付けに関して
日本社会教育学会 会員各位
7月1日より、2025年度(2024年9月~2025年8月まで)の「会費減額制度」の申請を受け付けます。
本制度のご利用を希望される会員は、下記の要領にて、学会HPの個人ページにある<会費減額申請システム>から申請してください。
なお、原則、申請年度ごとの受付となります。また、本年度から学会HPの個人ページ内にある<会費減額申請システム>からの申し込み受け付けとなっております。その点について、特に、ご留意ください。
【対象】学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等
【申請期間】2024年7月1日(月)~2024年8月15日(木)(期限厳守)
【申請方法】学会HPの個人ページにある<会費減額申請システム>から申し込む。
なお、「会費減額制度の概要」については、下記の添付ファイルを参照ください。
日本社会教育学会70周年記念国際シンポジウムの開催のお知らせ(追記:2024/07/19)
日本社会教育学会 関係各位
9月14日(土)16:00~19:20に日本社会教育学会70周年記念国際シンポジウムをオンラインにて開催いたします。
詳細については、開催要項をご参照ください。
70周年記念国際シンポジウム開催要項(確定版)20240716.pdf
皆様の多くのご参加をお待ちしております。
***
日本社会教育学会70周年記念国際シンポジウム
開催要項
1.主催・後援
l 主催:日本社会教育学会
l 後援:公益社団法人 全国公民館連合会
全国社会教育職員養成研究連絡協議会
社会教育推進全国協議会
日本公民館学会
公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会
2.テーマ
持続可能な社会づくりと社会教育:危機の時代における社会教育の課題
3.開催趣旨
今からちょうど20年前の日本社会教育学会50周年記念国際シンポジウムのテーマは、「社会教育と持続可能な発展:グローバル化するアジア地域における課題と可能性」でした。その趣旨文には、「第二次大戦後、日本では平和憲法と教育基本法にもとづき、学校教育とならんで社会教育の重要性が認識されてきました。人権を尊重し、市民の主体的な社会への参加を促進するために地方自治の本旨にそくして社会教育の制度化がはかられてきました。この根底には、社会の民主的な発展において社会教育がきわめて重要な役割を果たすという考え方があります」と書かれています。近年の日本及び世界の情勢を見ていると、社会教育法の制定から70年以上の歳月が経つ間、社会教育は社会の民主的な発展にどれくらい役割を果たしてきたのかについて考えさせられます。
今回の70周年国際シンポジウムのテーマは「持続可能な社会づくりと社会教育―危機の時代における社会教育の課題-」ですが、20年前と比べて持続可能性に対する議論や課題意識はいっそう高まっています。それは、日本国内の問題だけではなく、世界の共通課題の深刻さも増しているからです。
世界共通の喫緊の課題としては、まず気候変動やAI化の進展がもたらす環境及び労働に関わる問題が挙げられます。また、ウクライナ戦争をはじめ、東アジア諸国・地域を取り巻く戦争の恐怖、またそれに関連のある国家間の利害や権力の対立による世界平和の危機も大きな問題といえます。そして日本及び東アジア諸国・地域を中心とする少子高齢・人口減少問題や民主主義の衰退も対処すべき急務です。
70周年国際シンポジウムでは、私たちのいのちとくらしを脅かすような上記のさまざまな危機的課題の克服と、持続可能な社会づくりに向けて、社会教育は何ができ、どうあるべきかについて、成人教育・コミュニティ教育の分野で活躍する海外の研究者を招いて共に考え、議論したいと思います。
まず、近年日本社会にみられる民主主義の危機という課題から、民主主義と自治の主体形成における成人教育・社会教育の意義について検討する時間を持ちたいと思います。第二に、最近政策的に重要課題として浮上しているリスキリングに対応した生涯学習の再編の課題(労働にかかわる教育課題)について探りたいと思います。第三に、公定ナショナリズムに基づく社会再編に対するオルタナティブとしての社会像・国家像について考え、新たな社会教育のシステムを生み出す可能性について探求したいと思います。
4.開催日時と開催方法
2024年9月14日(土)16:00~19:20 (日本時間)
オンライン開催(同時通訳):参加申込済みの方に申込時に入力したメールアドレスに後日ウェビナーURLを送信します。
5.プログラム概要
・ 入室 15:45-16:00 Zoomへの入室
・ 開会式 16:00-16:20 司会:河野明日香(名古屋大学)・大高研道(明治大学)
主催者あいさつ 長澤成次(70周年記念事業実行委員会委員長)
報告者の紹介など 司会
・ 基調講演 16:20-16:35 宮﨑 隆志(日本社会教育学会会長・北海道文教大学)
「民主主義の再興のために-危機の時代における社会教育の意義と責任」
・ 報告 16:35-17:50
報告1: 16:35-17:00
Executive Director David Atchoarena (World Health Organization Academy)
「Community engagement for sustainable development: Lessons from the health sector」
報告2: 17:00-17:25
Prof. Petros Gougoulakis(Stockholm University)
「Social acceleration, Social stability and Learning for Transformation」
報告3: 17:25-17:50
牧野 篤(東京大学)
「重層的コミュニティ自治の試みと社会教育—根源的危機の時代に—」
・ 休憩 17:50-18:10
・ コメント: 18:10-18:40
コメンテーター1: 18:10-18:25 岡 幸江(九州大学)
コメンテーター2: 18:25-18:40 堀本麻由子(東洋大学)
・ 質疑応答・総括討論 18:40-19:10
・ 閉会式 19:10-19:20
閉会あいさつ 上野景三(前日本社会教育学会会長)
6.参加者
日本社会教育学会会員のほか社会教育職員、市民
7.参加費
一般:1,500円 学生・院生:1,000円
8.言語
日本語または英語(同時通訳)
9.参加申込(事前申込み必要)
研究大会の参加申し込み時(8月5日〜25日)に一緒に申し込んでください。
10.問い合わせ先
日本社会教育学会事務局
〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail:jssace.office◎gmail.com (◎を@に変えてください)
(祝祭日除く月・木曜日 10:30-16:30 リモートワーク中)
第71回研究大会(9月6日部分)の開催方法の変更について
日本社会教育学会 会員各位
9 月 6 日(金)~ 8 日(日)早稲田大学にて開催予定の「第71回研究大会」についてです。
学会通信(2024年第1号)のご案内ですと、6 日はオンライン、7・8 日は対面での開催と周知させて頂いておりました
その後の調整・検討の結果、9月6日(金)部分の開催方法を変更し、
下記の通り、全日程、対面での開催に変更になりましたので、ご報告いたします。
日本社会教育学会第71回研究大会
開催日時:2024年9月6日(金)~8日(日)
開催方法:早稲田大学にて対面開催(全日程)
事務局
『社会教育学研究』第60巻第2号への投稿原稿の募集
日本社会教育学会 関係各位
『社会教育学研究』第60巻第2号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第60巻第2号(2024年11月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。投稿にあたっては、『社会教育学研究』第59巻末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】
2024年6月1日(土)~2024 年6月30日(日)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、第60巻より年間2回の刊行となりました。今回は2号の募集となります。
【原稿種別について】
<一般>(これまでと同様の自由テーマによる論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・ 研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
・なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
<特集>(以下の特集テーマに基づいた論文)
・「研究論文」「実践報告」の2種類の原稿を募集しています。
・テーマ:障害をめぐる社会教育・生涯学習
・趣旨:障害をめぐる社会教育・生涯学習が、学校教育や社会福祉なども含めた多領域にまたがるテーマであることを前提とし、以下の観点に留意した論文を募集する。障害の社会モデルを念頭に置き、障害をめぐる社会教育・生涯学習実践が排除や分断を克服しようとする営みであると捉え、その実践において社会変革に向かう力が生じる過程にある学びのありよう、あるいはそうした学びを支える組織や制度のありようなどに焦点を当てた研究論文等であること。
【査読基準の公開】
・『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の留意点】
・ 本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。
・また、投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。特に連続投稿(投稿規程の3)、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
・近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
『社会教育学研究』第60巻第2号への投稿原稿の募集案内
日本社会教育学会 会員の皆様
『社会教育学研究』第60巻第2号(2024年11月末刊行予定)への投稿原稿募集のご連絡です。投稿にあたっては、『社会教育学研究』第59巻末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】
2024年6月1日(土)~2024 年6月30日(日)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、第60巻より年間2回の刊行となりました。今回は2号の募集内容となります。
【原稿種別について】
<一般>(これまでと同様の自由テーマによる論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
<特集>(以下の特集テーマに基づいた論文)
・「研究論文」「実践報告」の2種類の原稿を募集しています。
・第60巻2号の特集テーマは「障害をめぐる社会教育・生涯学習」になります。テーマの趣旨、執筆要領等の詳細については2024年3月発行の通信をご参照ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
緊急倫理研修会の開催について
日本社会教育学会 関係各位
9月8日に開催された研究大会のプロジェクト研究において、参加者から「差別的発言」がありました。学会として再発防止のため、下記のように緊急倫理研修会を開催します。
会員の皆様におかれましては是非受講して下さいますようお願い申し上げます。当日参加できない方は、後日録画した動画URLをお送りしますので、2024年5月31日(金)までにご覧いただきますようお願い申し上げます。
<緊急倫理研修会>
・内容:上野景三前会長「緊急研修会の開催趣旨と本件の経過報告」
生田周二先生「ヘイト・スピーチ問題と社会教育」(仮)
・司会:岡幸江副会長
・日時:2023年12月28日(木)14時〜15時30分
・開催方法:Zoomによる開催(※学会員に一斉メール配信したURLからお入りください)
【お知らせ】弁護士との顧問契約の締結について
会員各位
日本社会教育学会として弁護士と顧問契約を締結いたしました。つきましては、会員の皆さんに年間「1会員あたり30分」の無料法律相談(オンラインでも可能)ができることになりました。詳細は、会員ページの「会則・文章等」に格納されている文章をご覧ください。
第70回研究大会における差別的発言について(2023.9.28更新)
9月8日に開催されたプロジェクト研究において、参加者から「不適切な発言」がありました。
学会としては、倫理委員会を招集し、本発言を「差別的発言」にあたると判断いたしました。
今後、学会として再発防止に取り組むために、会員の倫理研修並びに研究大会運営の改善に引き続き取り組んでまいります。
日本社会教育学会
会長 上野景三
理事選挙の投票期間延長のお知らせ
学会からのメール配信に問題があり、多くの会員に理事選挙に関する情報が届いていないことが分かりました。
そのため、理事選挙の投票期間を当初の日程から2週間延長し、8月9日(水)までとします。
* 理事選挙について詳しくは、下記の記事をご参照ください。
https://www.jssace.jp/blogs/blog_entries/view/42/54806e6d6ae315e0e4b9d2378470dc26?frame_id=1953
(修正有)理事選挙インターネット投票開始のお知らせ
日本社会教育学会会員各位
2024-2025年度理事選挙のインターネット投票を開始しました。
インターネット投票は、短時間で簡単に投票することができます。
多くの皆様にご投票いただき、投票率向上にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
《投票期間》
6月26日(月)から7月26日(水)8月9日(水)まで
《投票方法》
学会ホームページ内の「理事選挙投票ページ」から投票してください。詳しい投票方法は「理事選挙投票ページ」に記載されています。
《理事選挙投票ページへのアクセス方法》
①学会ホームページにログインし、「個人会員ページ」に入ってください。
②サイドメニュー(スマートフォンの場合はページ下部のメニュー)の「個人会員ページ」の下に表示される「理事選挙投票ページ」からアクセスしてください。
《注意事項》
・「理事選挙投票ページ」からダウンロードできる「選挙のしおり」を必ずお読みください。
・「選挙のしおり」に記載されているご自身の所属ブロックをご確認ください。
・郵送での投票を希望された会員は「理事選挙投票ページ」にアクセスできません。別途、郵送にてご連絡差し上げます。
《問い合わせ》
インターネット投票についてご不明な点等がございましたら、学会事務局(jssace.office@gmail.com)までお問い合わせください。
2024年度「会費減額制度」申請について
日本社会教育学会 会員各位
2024年度(2023年に開催の総会後、2024年に開催の総会まで)の「会費減額制度」の申請を受け付けます。本制度のご利用を希望される会員は、下記の要領にて申請してください。
【対象】
・学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等(※本制度概要4参照)
【申請期間】
・2023年7月1日(土)~2023年8月15日(火)
【申請方法】
・申請書に必要事項を記入し事務局宛にメールで提出
*申請書は以下のリンクからダウンロードしてください。
《会費減額制度の概要》
1.本制度は、経済的な制約により学会加入が困難になる状況を少しでも改善することを目的として、個人への経済支援を行うものである。
2.本学会は、本人からの申請にもとづき年会費の減額を行う。
3.一年を単位として、年会費1万円を6,000円とする(4,000円の減額)。
4.申請者は、会費を払う年度において、学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等とする。本制度の主旨に則り、学術振興会の特別研究員、および、それに準ずる身分の者等、一定金額の収入のある者は申請できない。なお、申請者は、減額を受けようとする年度の前年度までの会費滞納のないことを要する(新規の入会者を除く)。
5.申請者は、所定の申請書に必要事項を記入し、事務局宛にメールで提出する。
6.申請期間は、毎年7月1日〜8月15日とする(必着)。新入会者は入会届とともに減額のための申請書を提出することができる。
7.本学会は、新年度開始後の理事会において申請者リストを回覧し、承認を行う。その後、事務局より承認の可否をメールにて申請者に通知する。
8.申請者は、申請の承認可否の結果を受けた後に当該年度の年会費を支払うものとする。
9.減額制度は一年ごとに適用する。申請は年度ごとに受けつける。
70周年記念事業募金活動について
日本社会教育学会創立70周年記念事業
募金趣意書
謹啓
益々ご清祥のことと存じます。
さて、日本社会教育学会は、1954年創立以来、新しい時代を築く社会教育実践に資するための研究の発展と交流に努め、2024年には70周年を迎えます。
第68回研究大会(運営:明治大学)がオンライン開催であったため、別日程で開催した総会において、70周年記念事業実行委員会を組織することが提案のうえ、承認されました。この総会での承認を受け、実行委員会(長澤成次委員長)では学会70年を総括し、これからの社会教育研究を展望していくためにどのような取り組みが必要か、準備を進めております。
現在、大まかな事業案として2024年9月に開催される研究大会にあわせて、(1)70周年記念出版、(2)国際シンポジウム開催、(3)資料集刊行の具体化のための議論を重ねています。これら事業の成功のために、学会として特別予算を組み、記念事業の円滑な遂行にあたろうとしていますが、多額の経費を要するため、百万円ほどは募金に依拠せざるを得ない状態です。記念事業を意義あるものにし、今後の社会教育の研究と実践の振興に寄与するためにはそのことに深い関心を寄せる会員や有志の方々のご協力が欠かせないものであり、その一環として募金をお願いすることによって、多くの人に支えられた事業として展開することが出来ると存じます。
どうか趣旨をお汲み取り下さいまして、ご協力を賜りますようお願いいたします。
謹白
2023年3月
日本社会教育学会70周年記念事業実行委員会委員長
長澤成次
日本社会教育学会会長・70周年記念事業実行委員会副委員長
上野景三
記
1、記念事業計画
(1)記念出版:2024年出版予定
(2)国際シンポジウム:2024年9月にオンラインで開催予定
(3)資料集刊行:2024年発行予定
2、募金概要
(1)募金目標額 100万
(2)一口 2,000円
(3)募金期間 2023年3月から2024年8月まで
(4)送金方法 以下に記載の銀行口座にお振り込みください。
みずほ銀行本郷支店(普通)1028164 日本社会教育学会
以上
事務局住所変更のお知らせ
2022年12月1日より、事務局の住所を変更いたします。
学会宛の郵便物は下記の住所へお送りください。
〒189-0012
東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
『社会教育学研究』バックナンバー引き取り希望募集
『社会教育学研究』バックナンバー引き取り希望募集
組織財政担当理事 秦範子
今期学会事務局移転に向けて理事会・組織財政では学会関係資料を整理し、電子データ化を進めています。これに伴い、近年刊行された『社会教育学研究』についてバックナンバーを希望する個人及び団体を募集します。
現在在庫があるのは以下のバックナンバーです。
48巻、49巻(1/2号)、50巻(1/2号)、51巻(1号)、52巻(1/2号)、53巻(1/2号)、54巻、55巻、56巻
ご希望される会員は氏名・所属・メールアドレス・送付先住所・電話番号、希望するバックナンバー(例:49巻1号)を明記の上、学会事務局までメール(jssace.office<at>gmail.com <at>を@に)にてご連絡ください。メールにて受付後、順次発送いたします。なお送料はご負担ください。
*受付期間は2022年11月30日までとします。
『社会教育学研究』への投稿案内及び「社会教育研究の動向」執筆者(グループ)の募集
日本社会教育学会 会員の皆様
『社会教育学研究』編集委員会からのお知らせです。
(1)ジャーナル59巻への投稿案内
投稿は,11月1日(火)から30日(水)の間,論文投稿システムで受け付けます。
今回,投稿種の変更や規程の改訂がありましたので,投稿までに58巻巻末の規程や,
学会からのお知らせ(下記URLのp.16-18)をご確認ください。
https://www.jssace.jp/wysiwyg/file/download/1/1723
投稿種が増え,研究レビューや事例研究,実践報告等を投稿しやすくなっておりますので,積極的にご活用ください。
(2)「2022年社会教育研究の動向」の執筆者(グループ)の募集
ジャーナルでは毎年,各大学院の院生が中心になり,研究動向を執筆いただいております。
しかし,近年になり執筆を担当できる大学院が減少していることから,今回より試行的に執筆者を募集することにしました。
締め切り・字数などの募集要項は添付するとおりです。年齢や所属による制限はありません。
申し込み期限は,2023年10月31日(月)までです。
ご参照の上,積極的にご応募をいただけますよう,どうぞよろしくお願いします。
募集要項-1.pdf
『社会教育学研究』59巻 編集委員会(担当:荻野・阿知良・斉藤・新矢・松本)
自由大学運動100周年記念集会東京集会のご案内
日本社会教育学会 会員各位
自由大学運動100周年記念集会東京集会のご案内
日本社会教育学会が後援をしております「自由大学運動100周年記念集会東京集会」のプログラムが完成しました。
集会の詳細につきましては、下記の添付ファイルをご覧ください。
自由大学運動100周年記念集会東京集会プログラム(完成版).pdf
2023年度「会費減額制度」申請について
2023年度(2022年に開催の総会後、2023年に開催の総会まで)の「会費減額制度」の申請を受け付けます。本制度のご利用を希望される会員は、下記の要領にて申請してください。
【対象】
・学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等(※本制度概要4参照)
【申請期間】
・2022年7月1日(金)~2022年8月15日(月)
【申請方法】
・申請書に必要事項を記入し事務局宛にメールで提出
*申請書は以下のリンクからダウンロードしてください。
《会費減額制度の概要》
1.本制度は、経済的な制約により学会加入が困難になる状況を少しでも改善することを目的として、個人への経済支援を行うものである。
2.本学会は、本人からの申請にもとづき年会費の減額を行う。
3.一年を単位として、年会費1万円を6,000円とする(4,000円の減額)。
4.申請者は、会費を払う年度において、学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等とする。本制度の主旨に則り、学術振興会の特別研究員、および、それに準ずる身分の者等、一定金額の収入のある者は申請できない。なお、申請者は、減額を受けようとする年度の前年度までの会費滞納のないことを要する(新規の入会者を除く)。
5.申請者は、所定の申請書に必要事項を記入し、事務局宛にメールで提出する。
6.申請期間は、毎年7月1日〜8月15日とする(必着)。新入会者は入会届とともに減額のための申請書を提出することができる。
7.本学会は、新年度開始後の理事会において申請者リストを回覧し、承認を行う。その後、事務局より承認の可否をメールにて申請者に通知する。
8.申請者は、申請の承認可否の結果を受けた後に当該年度の年会費を支払うものとする。
9.減額制度は一年ごとに適用する。申請は年度ごとに受けつける。
【日本学術会議からのご協力依頼】若手研究者をとりまく評価に関する意識調査(Webアンケート)
日本学術会議から調査協力の依頼がありました。
詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。
【ご協力依頼】若手研究者をとりまく評価に関する意識調査(Webアンケート).pdf
******
このたび、日本学術会議若手アカデミーでは、「若手研究者をとりまく評価に関する意識調査
(webアンケート)」を実施いたします。若手研究者のより良い研究・学術活動を可能にする
環境構築に向けた調査となりますので、以下の内容を貴学協会所属の研究者の方々(大学院生
や専門職を含む)に広く周知いただき、アンケートにご協力いただきますようお願い申し上げます。
【若手研究者をとりまく評価に関する意識調査(webアンケート)】
1.調査目的
世界的な競争、評価をめぐる問題、キャリアパスに関する課題など、若手研究者をめぐる研究・
知識生産の環境は多くの課題を抱えています。
この調査では、若手研究者にとっての評価について分析することで、知識生産をめぐるより良い
エコシステムの形成に寄与することを目的としています。
2.調査対象
45歳未満の若手研究者の方々(大学院生や若手の専門職を含む)
3.アンケートサイト
(1)URL(こちらからご回答いただけます。回答は任意です。)
https://r10.to/yaj2022
(2)所要時間:10分程度
(3)回答締切:2022年7月5日(火)
4.結果の公開
得られた結果は、学術的な分析を行った上で、報告書やオープンアクセス論文などの形で公開・
議論します。そして報告やデータに基づいた提案を、政策担当者をはじめ広く社会に共有していく
ことで今後の研究エコシステムのあり方とそのための科学技術・学術政策を考察するために積極的
に活用していきます。
また、ご回答いただいたデータは、個人が特定されない形で、多様な方の検討や学術的利用の
促進のためにオープンアクセス化を行います。
日本社会教育学会・国際交流委員会緊急企画 「今こそ平和・核を話そう―ウクライナ情勢から考える社会教育の語り・学びの場」のご案内
日本社会教育学会・国際交流委員会緊急企画
「今こそ平和・核を話そう―ウクライナ情勢から考える社会教育の語り・学びの場」
このたび緊急企画として、「今こそ平和・核を話そう―ウクライナ情勢から考える社会教育の語り・学びの場」(日本社会教育学会・国際交流委員会主催)を開催いたします。
今もなお、ロシアによる侵攻が続いており、多くのウクライナの人々の命が失われ、市民が悲惨な状況に置かれています。社会教育の実践と研究は、この危機に何ができるでしょうか。また、会員の皆様も新学期の授業や市民の学習の場でどのようにこの現実をとりあげたらいいのか悩まれているのではないでしょうか。
一方で、このような危機的状況下においてもウクライナの大学では授業をオンラインで可能な限り継続するなど、学生や市民の学びを止めない努力が日々なされているとのことです。そこでまずは、この危機に関する生涯学習・社会教育に携わる実践者・研究者としての悩みを共有しつつ、各会員がそれぞれの立場において何ができるかを考える機会を設けることといたしました。
緊急企画ということで、短時間ではありますが、ぜひとも多くの会員の皆様に参加いただければと考えております。
日本社会教育学会・国際交流委員会
記
日時:2022年4月30日(土)13:00-14:40 オンライン(Zoomによる配信)
参加申込:https://forms.gle/KLZmyQAmXPuQpgAN6 (申込〆切:4月29日12時)
※上記フォームよりお申込みいただき、後日申込者にZoomURLをお知らせします。
<登壇者>
ゲストスピーカー:
川崎哲氏(ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)国際運営委員/ピースボート共同代表)
人道上の危機と国際関係の危機、ロシアとウクライナ・東と西、核の脅威、東アジアへの影響、国際秩序と市民の役割、教育にできること。
<会員からの補論>
田中治彦会員(上智大学) SDGsと平和・核、社会教育
三宅隆史会員(シャンティ国際ボランティア会教育事業アドバイザー)難民支援活動と教育
コメンテーター:阿知良洋平会員(室蘭工業大学)
司会:近藤牧子・堀本麻由子(国際交流担当常任理事)
以上
 日本社会教育学会プロジェクト研究 新テーマの募集(応募要領)
日本社会教育学会プロジェクト研究 新テーマの募集(応募要領)
日本社会教育学会プロジェクト研究 新テーマの募集(応募要領)
1.本学会におけるプロジェクト研究の経緯・趣旨
プロジェクト研究は、日本社会教育学会において学会員主体の開かれた共同研究を進める重要な取り組みです。この研究では、社会教育が直面している重要な問題の課題を研究テーマとして設定し、定例の研究会を持ちながら3年程度をかけて研究します。学会員の多様な関心や問題意識を学会の組織的な研究活動に活かすために、学会員が共同で取り組むに値する重要テーマを募集・採択し、学会員主体の研究活動の推進と成果の共有化を図ることを目的としています。
日本社会教育学会では、学会の組織的な研究活動を実施するために、理事会が研究課題を設定する「宿題研究」が、行われてきました。その後、学会員の多様な関心や問題意識を学会の研究活動により反映させ、学会員の主体的参加を可能にするために、2000年代に入ってからは、学会として取り組む研究テーマを広く学会員に公募して決定し、学会員から研究チームを組織する「プロジェクト研究」に変更され、今日に至っています。
上記を踏まえ、新規プロジェクト研究テーマを以下の通り公募します。
2.応募資格
・日本社会教育学会会員であること。
・提案者は、個人・集団いずれも可能。ただし、テーマが採択された後には、研究チーム(以下、プロジェクト・メンバー)を組織することになります。なお、現在進行中の他のプロジェクト・メンバーが、新テーマのプロジェクト・メンバーになることは認められませんので、ご留意ください。
3.応募条件
・広く会員で研究・討議するにふさわしい、社会教育研究に関する学術的テーマであること(選考基準)。
・プロジェクト研究の期間は、3年間とします。
・6月集会・研究大会において、プロジェクト研究企画を実施運営すること。また、定例研究会を公開で開催するなど、学会員に開かれたプロジェクト運営を図ること。
・応募に関する不明点や不安な点について、研究担当理事への事前相談を歓迎いたします。状況に応じて、研究担当理事は既存のプロジェクト研究の経験紹介や学会員間のコーディネート等の支援を行います。
4.応募方法
応募を希望する者は、「プロジェクト研究 新テーマ提案書(応募様式).docx」を入手・作成の上、5月8日(日)までに日本社会教育学会事務局宛にメール添付で提出してください。
1)提案者の氏名・所属(集団で提案する場合は、責任者を明記する)
2)提案する研究テーマ
3)テーマ設定の趣旨
5.選考・採択後のスケジュール
応募のあった研究テーマについて、提案書に基づき理事会で審査いたします。理事会での協議によっては、複数のテーマの統合やテーマ名の変更が提案されることもあります。
結果は、研究大会における総会で、採択されたプロジェクト研究として発表されます。採択された研究テーマの責任者は、提案者だけでなく広く会員にも公募の上プロジェクト・メンバーを組織していただき、理事会での承認をえたのち、2023年6月に予定される6月集会から研究企画を実施していただくことになります。
照会・提出先:日本社会教育学会事務局(jssace.office◎gmail.com) ※◎を@に変更
 協力依頼|内閣府男女共同参画局ジェンダー統計ニーズ調査(Webアンケート)(3/14まで)
協力依頼|内閣府男女共同参画局ジェンダー統計ニーズ調査(Webアンケート)(3/14まで)
日本社会教育学会が加盟している「人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会」(GEAHSS略称ギース)より、下記のような内閣府男女共同参画局からのアンケート依頼がありましたのでご案内いたします。
ーーーーー
このたび、内閣府男女共同参画局では、ジェンダー統計に関するニーズ調査(Webアンケート調査)を行います。
つきましては、各種統計調査を使って調査分析を行う研究者の方々、大学の先生方、その下で分析を行う学生の皆様にも広く周知いただき、アンケートにご協力いただきますようお願い申し上げます。
1.調査目的
男女共同参画をさらに推し進めるには、男女の置かれている状況を客観的に把握するためのジェンダー統計を充実させ、データに基づいた施策を行うことが重要です。 現在、男女別で集計された統計・調査が増えてきていますが、政府統計、各種調査を利用して男女別に研究・分析をする際に、活用しづらい統計・表章、整備が不十分である統計・表章等を把握するため、ジェンダー統計に関するニーズ調査(Webアンケート調査)を行います。
2.アンケートサイト
(1)URL(こちらからご回答いただけます)
https://marketing.post-survey.com/gender_chosa2022/
(2)回答期日:令和4年3月1日(火)12:00~3月14日(月)23:59まで
【データの取り扱いについて】
委託会社のアンケートシステムを使いアンケートを実施し、入力いただいたデータ管理は内閣府において厳重に行います
3.調査実施主体
調査実施主体は、内閣府男女共同参画局です。また、本アンケート調査については、株式会社マーケティング・コミュニケーションズに委託しております。
株式会社マーケティング・コミュニケーションズ
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-4
gender-chosa◎mcto.co.jp ※◎を@に変更
お問い合わせは内閣府宛にお願い致します
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
併せてこちらの記事もご確認ください
・ 女性学・ジェンダー研究、セクシュアリティ関連研究者の最終講義について
・ 日本学術会議主催・日本教育学会共催 公開シンポジウム(5/5)中等教育からはじめよう!ジェンダー平等 ―誰一人取り残さない、誰もが暮らしやすい社会の実現をめざして―」のお知らせ(GEAHSSも共催)
・ 加盟学協会ジェンダー比率調査結果(2021年)
 「フィールドワークにおける性暴力・セクシュアルハラスメントに関する実態調査アンケート」回答ご協力のお願い
「フィールドワークにおける性暴力・セクシュアルハラスメントに関する実態調査アンケート」回答ご協力のお願い
日本社会教育学会が加盟している「人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会」(GEAHSS略称ギース)より、アンケートの協力依頼がありましたのでお知らせ致します。
************
共同研究グループ「フィールドワークとハラスメント(HiF)」では、フィールドワークという研究手法を採る研究者や学生が、フィールドで直面する性被害とその対策に関する実態把握のために、下記のアンケート調査を行います。被害事例に関する情報収集を通して、フィールドで起こる性暴力、セクシュアルハラスメントについての対策と啓発をより充実させていくことを目的としています。
なお、本アンケートは、学問分野ごとのフィールドワーク実施状況の調査、および被害防止のための事前学習の有無に関する調査を兼ねております。フィールドワークの定義は様々ですが、HiFでは「資料やデータの収集のために、研究者自らが研究室や研究機関を離れ、研究対象とする地域や団体など(フィールド)に赴き調査を行う研究手法のこと」と広く設定しております。このようなフィールドワークのご経験がある方は、性被害経験のない方も、ぜひ回答にご協力ください(これらの方々の回答の所要時間は、3~5分程度です)。
フィールドという研究機関を離れた場所でのハラスメントは実態把握が難しく、被害と対策の実態調査は、フィールドワークを行う学生や研究者のよりよい研究環境の構築・維持のため、またフィールドに学生を送り出すにあたり、教員が取りうる対策を検討する上でも有用です。お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
アンケートはこちら: https://safefieldwork.live-on.net/survey/purposes-of-this-survey/
(アンケート趣旨ページに飛びます。趣旨ページの末尾に、回答用URL(Microsoft Formsへのリンク)があります)
記
1.調査名:「フィールドワークにおける性暴力・セクシュアルハラスメントに関する実態調査アンケート」
2.調査目的:フィールドワーク中に起きた性暴力・セクシュアルハラスメントとその対策・対処についての実態把握
3.使用言語:日本語または英語
4. 回答所要時間:3~30分
5.実施時期:2022年1月15日~2022年2月15日(予定)
6.実施形式:Microsoft Formsを利用したウェブ・アンケート
7.倫理審査:名古屋大学倫理審査委員会による審査・承認済み(承認番号:NUHM-21-009)
8.実施主体:共同研究グループ「フィールドワークとハラスメント」(HiF)https://safefieldwork.live-on.net/
9. 後援:⼀般社団法人男女共同参画学協会連絡会 https://djrenrakukai.org/
人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(通称 GEAHSS) https://geahssoffice.wixsite.com/geahss
10.問い合わせ先:sub.fieldworkandsafety◎gmail.com (※◎を@に変更)
以上
フィールドワークとハラスメント(HiF)企画者一同
大友瑠璃子(北海道大学)、杉江あい(名古屋大学)、堀江未央(岐阜大学)、椎野若菜(東京外国語大学)、山口亮太(静岡県立大学/学振RPD)、蔦谷匠(総合研究大学院大学)、黄潔(名古屋大学)、稲角暢(京都大学/日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター)
日本社会教育学会年報第 66 集『高齢社会と社会教育』(仮題)原稿募集のお知らせ
日本社会教育学会年報第 66 集『高齢社会と社会教育』(仮題)原稿募集のお知らせ
日本社会教育学会では、1999年に年報『高齢社会における社会教育の課題』(1999年)を刊行したが、それから20年余が経過するなかで、当時とは異なる、高齢者や高齢者教育をめぐる情勢の変化が招来してきている。現在日本では、65歳以上の者の比率は29.1%(75歳以上15.0%)となり、逆に14歳以下の者の比率は11.8%と、少子化と連動した社会の超高齢化が進行している。団塊世代が後期高齢期を迎える、いわゆる2025年問題も間近に控え、介護や年金の問題も顕在化してきている。
他方で、公民館や放送大学などの社会教育・生涯学習実践の現場においても、多くの高齢学習者が参入していることがうかがえる。高齢者自身が運営する高齢者大学やNPOも誕生してきている。しかしこうした動向に呼応した社会教育あるいは高齢者学習支援のあり方は、まだ必ずしも十分に議論がなされているとはいえないようである。
これら一連の、高齢者をめぐる社会情勢の変化と社会教育実践現場での参加者層の変化に対応した学習支援の方途を探ることは、本学会における今日的かつ喫緊の研究課題だと考えられる。本年報は、以下の構成案に掲げる4つの柱を軸に、こうした社会の超高齢化のなかでの社会教育の果たす役割を再確認することをねらいとするものである。
本学会では、2018年10月から3年間かけて、プロジェクト研究「高齢社会と社会教育」を進めてきたが、他方で、本プロジェクト研究では取り上げられなかった重要な視点や課題も少なくない。本プロジェクト研究の成果をひとつの柱としつつも、新たな知見や研究・実践の成果をも盛り込んでいきたい。会員の皆様からの積極的かつ挑戦的な投稿を期待したい。
●構成(案)
第1部 高齢社会における社会教育の課題
現在進行中の日本社会の超高齢化がかかえる特徴と課題、およびそれらに対して社会教育がいかに貢献しうるのか、あるいは社会教育固有の課題は何かについて整理していく。ここでは少子化問題や後期高齢期問題をも射程に入れる。とくにここ20年くらいの間の社会の変化における、高齢者と社会教育の問題を焦点化する。
〈キーワード・テーマ例〉「超高齢化・少子化時代における社会教育」「高齢化の国際的動向」「高齢者の就労」「高齢期家族」「中山間地域における高齢者と社会教育」「高齢社会における地域自治」「高齢者に対する教育福祉」 など
第2部 高齢者の学習・教育をとらえる視点
社会の超高齢化の動向を念頭におきつつ、それと連動した高齢者学習支援や高齢者教育をとらえる、理論的視点を主に検討していく。高齢者教育の歴史的背景の研究や高齢者観の比較研究、高齢者の学習者特性、教育福祉論・教育老年学・社会老年学・生涯発達心理学などの研究領域からの知見との関連も検討していく。
〈キーワード・テーマ例〉「高齢者教育の歴史」「海外の高齢者教育」「高齢者学習支援の理論」「ライフヒストリーと経験知」「社会老年学領域の知見」 など
第3部 高齢者学習支援実践の展開
高齢者学習支援あるいは高齢者にかかわる社会教育実践から得られた知見や課題を明らかにし、高齢者に対する社会教育のあり方を探る。ここではとくに、高齢者が社会教育と直接かかわる部分や学習過程・プログラムなどを焦点化する。また高齢者学習支援に関する量的・質的な調査研究や実践分析の成果などをも念頭におく。
〈キーワード・テーマ例〉「高齢者大学の受講者」「高齢者がささえるNPO」「死への準備教育」「シニア・ボランティア」「回想法・自分史学習」「高等教育機関のシニア学生」「園芸療法」 など
第4部 社会の高齢化をささえる社会教育の条件整備論
ここでは第3部の高齢者学習支援実践をささえる、社会教育などの側の外在的な条件整備のあり方を取り上げる。高齢者学習支援実践を間接的にささえる制度設計や組織運営、社会教育職員の力量形成、学校教育におけるエイジング教育などの問題を念頭におく。
〈キーワード・テーマ例〉「認知症高齢者の社会参加」「高齢者大学運営上の課題」「第三期の大学のネットワーク」「高齢者学習支援の職員養成プログラム」「学校教育におけるエイジング教育」 など
●原稿募集に関して
①エントリー・応募要旨の提出
※本年報からエントリーおよび応募要旨は学会 HP電子投稿システムから提出していただきます。
〈応募要旨〉論文題名、要旨(章立て案を除き 2,500字以内)、章立て案。
・受付期間:2021 年 12 月 25日(土)〜 2021年 2 月1日(火)23 時 59 分。
・提出先:本学会サイト「『学会年報第 66 集』エントリーシステム」(会員ログインすると表示されます)。
・提出された応募要旨をもとに編集委員会で審査を行います。応募要旨には、執筆者が特定できる記載はしないでください。
・投稿資格は、2021 年度までの会費を納めている方です。
・エントリー受付後、受領メールが自動配信されます。メールが届かない場合は、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられていないかご確認ください。受領メールが届かなかった際は年報事務局(nenpo66@gmail.com)にご連絡ください(※本メールは提出先ではありませんのでご注意ください)。
②採否の通知について
・採否の結果は、2 月下旬までに応募者に連絡します。採択された方には執筆要綱をお送りします。
③原稿送付
・原稿字数は 12,000 字以内 ( 図、表を含む )。公募原稿は日本語のみとする。
・締切:2022 年 5 月 6 日 (金)。
・要旨が採択されても、完成原稿の査読結果によっては、修正を求められることや掲載されないこともあります。
・掲載後、公募論文については、要望があれば査読証明を発行します。
(年報第 66 集編集委員会)
第7回ユネスコ国際成人教育会議にむけたナショナルミーティングのご案内
本学会が企画協力をしているプログラムのご案内です。
来年6月の第7回ユネスコ国際成人教育会議の開催に先立ちまして、以下のプログラムが
認定NPO法人開発教育協会(DEAR)により、予定されております。
会員資格問わずにどなたでも参加申し込みができますので、ご関心のある方はご参加ください。
なお、本プログラムの詳細については、添付のチラシ(ale_flyer_1210.pdf)も併せて参照ください。
ーーーー以下、開催案内ーーーーーーーー
人の一生のほとんどは「成人期」であるのにもかかわらず、今の社会では、おと
なの学び(成人教育)の機会は重視されているとは言えません。
社会での意思決定に対して、明らかに力を持つおとなたちが学び続けなけれ
ば、よりよい社会をつくることはできません。改めて、おとな・ユースの学びに
ついて、一緒に考えるため、本会合を開催します。
開催概要
----------------------------------
「社会教育・成人教育の課題と展望〜おとな・ユースの学びを取り残さない」
(第7回ユネスコ国際成人教育会議にむけた ナショナルミーティング)
http://www.dear.or.jp/event/8382/
----------------------------------
▼日時
2022年2月5日(土)13:00-17:00
▼対象
社会教育実践者・研究者、NGO/NPO関係者、テーマに関心のある方
▼定員:100名程度(先着順・要事前申し込み)
▼会場
オンラインにて開催(zoom)
※参加をご希望される方に、後日URLをご案内します。
▼参加費
無料
▼プログラム
全体会では、国内の有識者に社会教育・成人教育の現状課題と展望を提起してい
ただきます。分科会では、「2015年勧告」における三つの重点領域である
「アクティブ・シティズンシップスキル」「識字・基礎スキル」「継続教育・職
業スキル」に分かれて議論します。
1. 全体会 13:00-14:30
「社会教育・成人教育の課題と展望〜おとな・若者の学びを取り残さない」
ユネスコ国際成人教育会議の概要や、国内の社会教育・成人教育の現状課題と展
望を有識者から提起していただきます。
司会:片岡麻里(ガールスカウト日本連盟)
あいさつ: 青柳茂(ユネスコ・アジア太平洋地域教育事務所 所長)
パネリスト:
・文部科学省(調整中)
・上野景三(日本社会教育学会会長/西九州大学)
・岡田敏之(基礎教育保障学会会長/同志社大学)
・近藤牧子(DEAR副代表理事)
2. 分科会 14:40-16:40(選択制)
▼第1分科会: アクティブ・シティズンシップを育む教育とは
地域の社会教育やNGOによる市民性や市民参加を培う教育活動について考えま
す。<アクティブ・シティズンシップスキル>
司会:近藤牧子
発表者:
・的野信一(板橋区教育委員会)
・宮城潤(那覇市若狭公民館 館長)
・内田聖子(アジア太平洋資料センター共同代表)
▼第2分科会:識字教育・基礎教育の実践から
国内外での識字教育や基礎教育について、夜間中学などの実践から教育保障につ
いて考えます。<識字・基礎スキル>
司会:大安喜一(ユネスコ・アジア文化センター)
発表者:
・工藤慶一(北海道に夜間中学をつくる会共同代表)
・菅原智恵美(日之出よみかき教室(木)、識字・日本語センター)
・小荒井理恵(教育協力NGOネットワーク)
▼第3分科会:エンパワメントのための職業教育
資格や職業技術獲得のための教育や研修に留まらない、ライフスキルとしての職
業教育、女性のエンパワメントなどについて考えます。<継続教育・専門性発展
(職業スキル)>
司会:中村絵乃(DEAR)
発表者:
・文部科学省(調整中)
・正井禮子(認定NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべこ)
・三宅隆史(シャンティ国際ボランティア会)
3. 全体会 16:40-17:00
各コーディネーターからの報告とまとめ
進行:近藤牧子
▼申込方法
http://www.dear.or.jp/event/8382/
※1月25日(火)締切
▼背景
2022年6月にモロッコで第7回ユネスコ国際成人教育会議が開催予定です。これ
は、12年に一度開催される、成人教育に関する貴重な国際会議となります。これ
までの会議の成果文書では、全ての人に対して個人をエンパワーする学習保障
と、持続可能な社会構築を推進するための理念や具体策が記されてきました。
また、2015年の国連総会で採択されたSDGsの教育目標である、SDGsの目標4(質
の高い教育を全ての人に)達成において、成人教育の推進は不可欠です。しか
し、世界でも日本でも教育施策における成人教育への比重は決して高いとは言え
ません。
本イベントでは、第7回会議に向けて、日本の成人教育への関心喚起を目的と
し、第7回会議の趣旨や、その鍵となる2015年にユネスコ総会採択された、「成
人学習・教育に関する勧告(通称:2015年勧告)」の理解共有を図ります。
▼主催
認定NPO法人開発教育協会(DEAR)
▼協力
基礎教育保障学会、日本社会教育学会 、教育協力NGOネットワーク(JNNE)
▼後援
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
▼助成
独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金
▼本件に関するお問い合わせ
開発教育協会(DEAR)
事務局担当:伊藤 E-mail: yito◎dear.or.jp ※◎を@に変更
※在宅勤務を行っています。
日本社会教育学会年報第66集『高齢社会と社会教育』(仮題)原稿募集に関するお知らせ
先の日本社会教育学会総会にて、次期年報第66集のテーマが「高齢社会と社会教育」(仮題)として決定し、その後常任理事会で同年報編集委員を決定し、11月23日に年報編集委員会を発足しました。
12月の学会通信にて年報原稿の募集を行い、各会員からエントリーしていただくのが通例の手続きなのですが、今期の場合、通信の発行が12月末に予定されており、会員への周知期間が不十分ではないかという危惧もあります。そこで今回、全会員を対象に、次期年報の編集方針と応募内容・スケジュール(あくまで予定)をお知らせし、12月末発行予定の「学会通信」にて正式な募集をさせていただくことにしました。
「高齢社会と社会教育」に関心があり、原稿執筆を希望する会員は、下記をご参照いただき、ご準備を進めていただけると幸いです。
年報第66集『高齢社会と社会教育』(仮題)編集方針
1999年学会年報『高齢社会における社会教育の課題』の刊行から20余年が経過した。その後急速に進んだ社会の超高齢化の動向を踏まえ、それに呼応した社会教育の研究・実践上の知見と課題を整理し、今後の社会教育研究の在り方を提言することをめざす。そのための編集方針として、以下に挙げる4つの柱を掲げることとした。
①高齢社会における社会教育の課題
②高齢者の学習を捉える視点
③高齢者学習の実践の展開
④社会の高齢化をささえる社会教育の側の条件整備
これらの柱に則って社会の高齢化の状況・診断とそれらに対する社会教育の果たす役割を軸に、本年報を編集していく。
2021年11月23日 年報第66集編集委員会 決定
なお、原稿の応募スケジュールとしては「論文題目・要旨(章立て案を除き、2,500字以内)、章立て案」を作成し、2022年2月1日(火)23時59分までに、本学会サイト『学会年報第66集』にエントリーして申し込むこととなっております。
ぜひ、多くの会員のみなさまの応募を期待しております。
2021年11月25日
年報編集担当 常任理事 梶野 光信
長岡 智寿子
全国理事 堀 薫夫
2022-2023年度「幹事」の募集について
2022-2023年度「幹事」の募集について
この度、日本社会教育学会では、学会運営をサポートしていただく「幹事」を募集することになりました。
本学会は選挙で選ばれた理事が中心となり、業務を分担しながら運営されております。この各担当理事の業務のサポートが、幹事の基本的な役割となります。
幹事をご担当いただきますと、常任理事会や全国理事会にご出席することになりますので、学会の最新の研究動向を知ることができ、また主たる研究課題をめぐる議論に加わることができます。さらに、理事をはじめキャリアのある会員との研究交流の機会を得られる等の利点があります。学会としましても、幹事の皆様に各業務のサポート役を担っていただきながら学会運営の内実に触れていただき、将来的に学会の中核的な担い手になっていただくことを期待しております。
従来は首都圏の大学院生や若手会員が幹事を担ってきましたが、学会運営の多くがオンライン化されたことを受け、広く全国から募集することになりました。該当する会員の皆様におかれましては、ふるってご応募いただけますと幸いです。
応募条件 学会加入歴10年以内の会員
募集人数 6名程度
業務内容 各担当理事の業務補助 ※各担当の業務内容は幹事募集要項2022-23.pdfをご参照ください。
業務期間 2022年1月から2023年9月開催予定の総会まで
応募方法 下記のリンク先(Googleフォーム)にて必要事項をご入力ください
https://forms.gle/saS4NuoFxoVt6GWd8
応募締切 2021年12月10日(金)
採否通知 12月下旬(予定)
【リマインド】「会費減額制度」の申請期限について
日本社会教育学会では、2022年度(2021年開催の総会後)より、学生及び常勤職にない会員等の年会費を減額する制度を導入します。過日、標記の案内を配信致しましたが、10月末日までが申請期間となっております。申請方法など詳細については、下記の学会HPを参照ください。
https://www.jssace.jp/blogs/blog_entries/view/42/8fd1b250b489be5b69e19be44f26d5f8?frame_id=1953
『社会教育学研究』第58巻 論文電子投稿システム稼働のお知らせ
日本社会教育学会会員各位
『社会教育学研究』第58巻(2022年6月発行)論文電子投稿システムが、11月1日~11月30日まで稼働しております。
投稿を予定されている会員の皆様は、期日内に投稿いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、投稿にあたりましては、2021年度会費を完納していることが条件となっております。
また、第57巻より、投稿システム画面の入力項目に、投稿規程・執筆要領の遵守確認が追加されました。
投稿予定者は、あらかじめご確認ください。
 「会費減額制度」導入のお知らせ
「会費減額制度」導入のお知らせ
日本社会教育学会では、2022年度(2021年開催の総会後)より、学生及び常勤職にない会員等の年会費を減額する制度を導入します。概要は以下の通りです。
1.本制度は、経済的な制約により学会加入が困難になる状況を少しでも改善することを目的として、個人への経済支援を行うものである。
2.本学会は、本人からの申請にもとづき年会費の減額を行う。
3.一年を単位として、年会費1万円を6,000円とする(4,000円の減額)。
4.申請者は、会費を払う年度において、学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等とする。本制度の主旨に則り、学術振興会の特別研究員、および、それに準ずる身分の者等、一定金額の収入のある者は申請できない。なお、申請者は、減額を受けようとする年度の前年度までの会費滞納のないことを要する(新規の入会者を除く)。
5.申請者は、所定の申請書に必要事項を記入し、事務局宛にメールで提出する。
6.申請期間は、毎年7月1日〜8月15日とする(必着)。ただし、2022年度(2021年度会員総会(2021年9月25日)以降、翌2022年9月(予定)の会員総会まで)のみ、2021年10月1日から10月末日まで申請期間とする。新入会者は入会届とともに減額のための申請書を提出することができる。
7.本学会は、新年度開始後の理事会において申請者リストを回覧し、承認を行う。その後、事務局より承認の可否をメールにて申請者に通知する。
8.申請者は、申請の承認可否の結果を受けた後に当該年度の年会費を支払うものとする。
9.減額制度は一年ごとに適用する。申請は年度ごとに受けつける。
*申請書は以下のリンクからダウンロードしてください。
*上記「会費減額制度」の設置に伴い、下記の通り会則を変更いたしました。
(旧)
第8条 会員は会費(学会誌「社会教育学研究」、学会年報を含む)を納入するものとする。会費は、会員は年額10,000円、団体会員は年額6,000円とする。会費の納入期限は当該会計年度の8月31日とする。新たに入会した者は、その年度の会費を納入するものとする。
↓
(新)
第8条 会員は会費(学会誌「社会教育学研究」、学会年報を含む)を納入するものとする。会費は、会員は年額10,000円、団体会員は年額6,000円とする。ただし、学生及び常勤職にない会員で理事会に認められた者については年額6,000円とする会費減額制度を利用することができる。会費の納入期限は当該会計年度の8月31日とする。新たに入会した者は、その年度の会費を納入するものとする。
全国大学院生協議会(全院協)からのアンケート依頼について
日本社会教育学会会員のみなさま
件名について、全国大学院生協議会より、大学院生会員のみなさま宛にアンケートの協力依頼がありました。
ぜひご協力ください。
事務局
::::::::::::::::::
大学院生のみなさま
突然のご連絡、失礼いたします。私たちは全国大学院生協議会(全院協)です。
この度は、大学院生を対象にしたアンケート調査にご協力いただきたく、ご連絡いたしました。
本調査は、全院協が、全国各大学の加盟院生協議会・自治会の協力の下に実施する、全国規模のアンケート調査です。本調査は、大学院生の研究及び生活実態を客観的に把握し、もってその向上に資する目的で行うものです。
全院協では2004年度以来毎年、アンケート調査を行っており、今年で17回目です。調査結果は「報告書」としてまとめており、こうした調査結果をもとに関連省庁、国会議員及び主要政党等に対して、学費値下げや奨学金の拡充などの要請を行っております。また、本調査により明らかになった大学院生の深刻な実態は、これまで、NHKや朝日新聞をはじめとした各種マスメディアでも取り上げられ、社会的に大きな反響を呼びました。
大学院生の奨学金借入、「500万円以上」が25%
朝日新聞 2014年11月27日 朝刊
全国大学院生協議会まとめ 大学院生、6割が経済不安
毎日新聞 2014年12月1日 朝刊
大学院生 バイトで研究に支障
NHK生活情報ブログ 2012年11月30日
http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/800/139365.html
学費・奨学金等の重大な問題が存在するにも関わらず、大学院生の生活実態を詳細に明らかにする全国的な調査は、全院協以外では行なわれておりません。より多くの方々に回答いただき、調査の精度を高め、問題を広く社会に発信していくことの意義は今日一層高まっていると考えます。とりわけ今年度はコロナ禍が大学院生の研究生活にどのような影響を与えたかを測る上で、例年以上に重要な意義を帯びてくるのではないかと予測されます。ぜひご協力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
本アンケート調査で得られた情報は、以上に述べた目的以外に使用されることはありません。また、個人が特定される形で調査結果をまとめることはありません。
回答はこちらから行うことができます。
―――――――――――――――――――――
【アンケート回答フォームURL】
https://forms.gle/9GhLr3R2L6p6uWMv8
―――――――――――――――――――――
期限は【2021年9月30日】です。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力よろしくお願い致します。
全国大学院生協議会
〒186-0004 東京都国立市中2-1 一橋大学院生自治会室気付
電話・FAX:042-577-5679
E-mail:zeninkyo.jimu◎gmail.com ※◎を@に変えてください
Twitter:@zeninkyo
Facebook:https://www.facebook.com/zeninkyo/
Website:https://zeninkyo.org/ (上記アンケートのURLが開けない場合はこちらから)
:::::::::::::::::::::::::
令和5年度以降の科研費審査区分表(内容の例)等に関する意見募集の実施について
日本社会教育学会会員のみなさま
件名について、以下のように意見募集が行われております(9月5日締め切り)。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1385136_00002.htm
本会については、「審査区分表(内容の例)見直し案」のうち、「中区分9:教育学関連分野」、小区分09010の見直しが全体に関わります。
詳細につきましては上記ページをご確認ください。
事務局
「ジャーナルと年報の今後のあり方についてー議論のまとめ(最終版)ー」に関する意見の募集
日本社会教育学会会員のみなさま
今期理事会では、ワーキンググループを組織し、ジャーナルと年報の今後のあり方の見直しを行ってまいりました。
理事会での検討を踏まえて議論のまとめを整理のうえ、以下のように三役から会員のみなさまと共有いたします。
「ジャーナルと年報の今後のあり方について(議論のまとめ)」.pdf
このまとめについて、会員のみなさまからのご意見・ご質問を募集いたします。
ご意見・ご質問につきましては、下記のフォームよりお寄せください。
【ご意見・ご質問投稿先】
https://forms.office.com/r/3U5UvmpHjR
総会(9月25日開催)までのスケジュールから、ご意見・ご質問につきましては、恐れ入りますが8月31日(火曜日)中にお願いをいたします。
事務局
「倫理委員会規定」改訂、および、「倫理委員会に関する細則」策定について
倫理委員会では、「倫理委員会規程」の改訂(2021年7月19日付)を行い、会員の相談対応のための「倫理委員会に関する細則」(7月22日付)を策定しました。
「相談申込書」を併せてホームページに掲載しました。
プロジェクト研究新テーマの募集期間延長のお知らせ
プロジェクト研究新テーマの募集期間を5月末まで延長いたします。会員のみなさまの応募をお待ちしています。
1.本学会におけるプロジェクト研究の経緯・趣旨
プロジェクト研究は、日本社会教育学会の研究活動として社会教育に関する研究テーマについての共同研究を行うものです。共同研究は、学会員によって研究チームを組織し、定例の研究会を持ちながら3年程度をかけて実施します。研究テーマは、個人やグループによる会員から広く募集をし、理事会における審査を経て採択されます。
日本社会教育学会が実施するプロジェクト研究は、研究成果が会員相互に共有され、広く社会に公表されることにより、社会教育に関する研究の進展と実践に寄与することを目的としています。そこで、以下の通りプロジェクト研究のテーマを公募いたします。
2.応募資格
・日本社会教育学会の会員であること。
・応募は、個人・グループのいずれも可能。
3.応募条件
・広く会員で研究・討議するにふさわしい、社会教育研究に関する学術的テーマであること。
・研究チーム(プロジェクト・メンバー)を組織して実施する共同研究であること。
・6月集会・研究大会において、研究企画を実施すること。また、定例研究会を公開で開催するなど、学会員に開かれた研究活動を推進すること。
4.応募方法
応募を希望する者は、「日本社会教育学会プロジェクト研究 新テーマ提案書(様式あり)」(学会ホームページより入手)を作成の上、5月31日(月)(必着)までに日本社会教育学会事務局宛にメール添付で提出してください。
1)提案者の氏名・所属(グループで提案する場合は、代表者を明記する)
2)提案する研究テーマ
3)テーマ設定の趣旨
5.スケジュール
応募のあった研究テーマについて、提案書に基づき理事会で審査いたします。理事会での協議によっては、複数のテーマの統合やテーマ名の変更が提案されることもあります。
結果については総会で採択されたプロジェクト研究を発表します。採択された研究テーマの代表者は、研究チームを組織してください。プロジェクト・メンバーの選定にあたっては、広く会員からも公募してください。2022 年6月に予定される6月集会から研究企画を実施してください(キックオフ)。
照会・提出先:日本社会教育学会事務局(jssace.office◎gmail.com ※◎を@に変えてください)
研究倫理と差別・ハラスメントに関する会員アンケート
日本社会教育学会会員各位
日本社会教育学会は、真理の追求、人間の尊厳および基本的人権の尊重が、研究をはじめとするすべての学会活動の基盤となること、とりわけ、不正な目的、方法による研究は学問的真理への道を閉ざすものであり、権威や権力の濫用は学問の自由な発展とは相容れないものであることから、不正な研究や差別・ハラスメントの防止に努めることが学会および学会員の倫理的義務であるとして、2012年に日本社会教育学会倫理宣言を採択しました。
その後、学会内に常設の倫理委員会を設置するとともに、研究大会や六月集会において継続的に研修会を実施してきました。このアンケートは、このような本学会のこれまでの取り組み、および今後の活動に関して、会員の皆さんのご意見をうかがうものです。
このアンケートへの回答は統計的に処理します。データ分析の際に誰がどのような回答をしたかを特定したり、あるいは特定できるような形で回答結果を公表したりすることは一切ありません。回答へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
2020年10月20日
日本社会教育学会倫理委員会
安藤聡彦、大村隆史、生島美和、久保田治助、
辻智子、久井英輔、村田晶子
■回答方法:Googleフォームにて送信(https://forms.gle/XMDbBXA1nqing6em8)
■締め切り:12月末日
■問い合わせ:日本社会教育学会倫理委員会委員・副会長村田晶子 akikom◎waseda.jp ※◎を@に変えてください
<事務局員の勤務について>
事務局は事務局は祝祭日を除く(月)・(木) 10:00~16:00 リモートワークのため、電話受付はしておりません。お問合せ等はメールにてご連絡ください。
【事務局メール: jssace.office@gmail.com】
ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【会費振込先】今年度(2026年度)が2025年9月から始まっています。会費納入状況は各自個人画面で確認の上、会費未納分と今年度分の会費の振込みをお願いいたします。尚、2026年度会費減額申請は受付終了しています。2027年度については2026年7/1(水)~2027年8/15(土)です。減額希望の会員は期間内に<会費減額申請システム>から申請し、承認の連絡が来次第、会費の納入をしてください。(10月開催予定の理事会で承認後ご連絡いたします。)
ゆうちょ銀行 振替口座 00150-1-87773
他金融機関からの振込用口座番号:〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座0087773
*口座振替ご希望の方 個人ページにアクセスした後、下方<会則・文書等>にあります「預金口座振替依頼書」に必要事項を入力後プリントアウトし、押印したものを学会事務局までご郵送ください。今年度(2026年度)は2025年10月15日必着で〆切りました。
*領収書が必要な方 会費等の領収書が必要な方は、メールにて領収書の宛名・送付先をお知らせください。
◎会員の方は各自、登録メールアドレスの確認をお願いいたします。
「六月集会プログラム」「学会からのお知らせ」「研究大会プログラム」はネット配信のみになります。
〒189-0012
東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail:jssace.office◎gmail.com
(◎を@に変えてください)
(祝祭日除く月・木曜日 10:30-16:30 リモートワーク中)
Tel:090-5782-1848 ※現在電話受付停止中