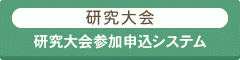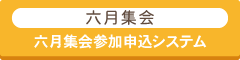会員企画のお知らせ
J-CEF主催「第13回シティズンシップ教育ミーティング 」のご案内
会員より、以下の案内がありましたので情報提供いたします(転送・転載歓迎)。
----------------------------------
日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)主催
第13回シティズンシップ教育ミーティング
「『18歳選挙権』からの10年をふりかえり,次の10年の課題をみわたす。
〜市民の政治参加/社会参加を巡る学びはどう変わったのか?〜」
2026.3.8, TOKYO
--------------------------------------
https://jcef.jp/project/cemt13.html
選挙権年齢が18歳に引き下げられてから10年が経ち、私たちの視点からは何が見えるでしょうか?
振り返ってみれば、選挙権年齢の引き下げをきっかけの一つとしてシティズンシップ教育の実践は多様な広がりを見せることになりました。たとえば、ジェンダー平等やソーシャル・インクルージョン、多文化共生やポストコロニアリズム、不登校、子ども・若者参画、まちづくり、デジタル・シティズンシップといったテーマがシティズンシップ教育でも存在感を高めることになりました。また、それらが展開される場として学校教育、社会教育、社会福祉、ユースワークなど従来の場に加え、異分野との連携など新しい場の登場も見られます。こうした広がりは、「投票行動のみならずどういう形で政治/社会に参画するのか」「社会を構成する『われわれ』とは誰のことなのか」「異質な他者と共にどう社会をつくるか」といった問いの広がりとも言えるでしょう。
一方で国内外では社会の分断/分極が進み、攻撃的な言葉が飛び交う場面も少なくありません。民主主義の基盤に揺らぎが見られる今だからこそ、シティズンシップ教育の根幹を捉えつつ、現在見えている「広がり」の意味を積極的に汲み取っていく必要があるのではないでしょうか。自らの声を伝えること、他者の声を聴くこと、そして、折衝しながらお互いの自由を守ること——これらを重ね合わせる営みがますます重要になっています。
この10年、私たちは何を進めることができたのでしょうか。そして、何を見落としてきたのでしょうか。今年の「シティズンシップ教育ミーティング」では、ドイツからのゲストも招聘して、国内外の動向から、これらの問いにともに向き合います。
全体会の流れを受ける形で分科会では、現代の政治的動向を踏まえて求められる政治的素養について検討したり、学校の地域連携/社会連携のネクストステージを見渡したり、ジェンダー視点からシティズンシップ教育を再考したりする場を設けます。
実践者や研究者、政策形成者、学生といった垣根を越えてシティズンシップ教育について対話する場を設けることを通じ、これからの10年を考え、活力を持ってそれぞれの現場に臨める、そうした機会になればと願っています。みなさまのご参加をお待ちしております。
■日時:2026年3月8日(日)10時〜18時
(交流会:18時30分〜20時,任意参加)
(開場:9時30分 / 閉場:20時30分)
■場所:東洋大学 白山キャンパス 8号館
アクセス:https://www.toyo.ac.jp/nyushi/about/campus/hakusan/access.html
■プログラム
09:30 開場
10:00 オープニング
10:20 全体会
◉「『18歳選挙権』からの10年をふりかえり,次の10年の課題をみわたす。
−市民の政治参加/社会参加を巡る学びはどう変わったのか?−」
--------------------------------------------------------------------------
■イントロダクション(10分)
宇恵野珠美さん(中央大学法学部)
■キーノートスピーチ
<日本の10年>
大畑方人さん(自由学園中学部高等部教諭)
西野偉彦さん(第一生命経済研究所主任研究員,神奈川県教育委員会「小・中学校における政治的教養を育む教育」座長)
古野香織さん(認定NPO法人カタリバ みんなのルールメイキング課題解決ユニットリーダー)
<ドイツの10年>
ゲルノート・ヴォルフラムさん(マクロメディア大学教授/ドイツ連邦政治教育センター(bpb)特別顧問)
クリスティアン・ヨハンさん(ヨーロピアン・アカデミー・ベルリン(EAB)理事長)
■ファシリテーター
金杉龍吾さん(一橋大学大学院社会学研究科修士課程)
住友翔馬さん(広島大学教育学部)
12:30 昼食休憩
13:30 分科会
◉第一分科会「現代の政治動向から求められる政治的素養とは?」
--------------------------------------------------------------------------
■ゲスト
杉田淳さん(NHK報道局選挙プロジェクト)
岡田泰孝さん( 価値判断力・意思決定力を育成する社会科授業研究会副代表)
星野真澄さん(明治学院大学文学部准教授)
■コーディネーター
小野太郎さん(伊丹市立摂陽小学校教諭)
黒崎洋介さん(神奈川県立横浜瀬谷高等学校教諭)
原田伊織さん(NPO法人ASK理事)
宮﨑一徳さん(みんなの政策研究所)
◉第二分科会「これからの学校と地域の連携は何を目指すのか?
:シティズンシップ教育と探究学習の視点から」
-------------------------------------------------------------------------
■ゲスト
平田正英さん(株式会社Qareer CEO/CTO)
村宮汐莉 さん(菊川市地域おこし協力隊)
■コーディネーター
猪股大輝さん(東洋大学文学部教育学科助教)
住友翔馬 さん(広島大学教育学部)
◉第三分科会「女性のいないシティズンシップ教育?」
--------------------------------------------------------------------------
■ゲスト
前田健太郎さん(東京大学大学院法学政治学研究科教授)ほか
■コーディネーター
別木萌果さん(都立小川高等学校教諭)
◉第四分科会「高校生・大学生発表セッション」(発表者を公募します!)
--------------------------------------------------------------------------
■コメンテーター
中平一義さん(東洋大学文学部教育学科教授)
古田雄一さん(筑波大学人間系助教)
川口広美さん(広島大学大学院人間社会科学研究科准教授)
■ファシリテーター
古野香織さん(認定NPO法人カタリバ みんなのルールメイキング課題解決ユニットリーダー)
本セッションでは,高校生・大学生から研究報告や実践報告を募ります。
発表を希望される方は以下フォームから発表内容をご入力ください(必須)。
https://forms.gle/WpkXh2LFWLV4Mf4Q9
(1)研究報告 シティズンシップ教育や、市民の社会創造の参画にかかわる調査/研究の報告を募集します。報告にあたっては、取り上げる問題、用いた手法、主たる結論、新たな知見などをまとめてください。単なる「調べ学習」で終わらず、オリジナルな発見や考えを含めてください。
(2)実践報告 高校生や大学が取り組んだ社会参加/政治参加の実践活動や学習活動、シティズンシップ教育を推進する活動等にかかわる経験や成果報告を募集します。報告にあたっては、取り上げる実践の背景や内容、主たる成果、課題等をまとめてください。単なる体験談で終わらず、実践を通じて見出された発見や成長を含めてください。
*1発表につき持ち時間の目安は30分(発表時間15分~20分、質疑応答15分~10分)です。
*発表の順番は、当日お示しいたしますので、それにお従いください。
*発表時間だけではなく,大会の全プログラムにご参加ください。
*報告に際して、旅費・謝金等は一切支給いたしません。
15:30 休憩・移動
15:45 全体会(2):対話セッション
--------------------------------------------------------------------------
■ファシリテーター
金杉龍吾さん(一橋大学大学院社会学研究科修士課程)
住友翔馬さん(広島大学教育学部)
■コメンテーター
川口広美さん(広島大学大学院人間社会科学研究科准教授)
ゲルノート・ヴォルフラムさん(マクロメディア大学教授)
クリスティアン・ヨハンさん(EAB理事長)
17:20 クロージング
--------------------------------------------------------------------------
■メッセージ
小玉重夫さん(白梅学園大学学長・東京大学名誉教授)
■ファシリテーター
川中大輔さん(関西学院大学人間福祉学部専任講師)
18:00 終了
18:30 交流会(任意参加)
20:00 交流会終了
20:30 閉場
■対象:シティズンシップ教育や本企画に関心のある方であれば,どなたでも参加を歓迎いたします。
■定員:120名(先着順)
■参加費:
・一般:3,000円
・大学生・院生:1,000円
・高校生以下:無料
・交流会(任意参加)(一律):2,500円
■参加申込:
2026年3月5日(木)までに、以下参加申込みページからオンラインでお申し込みください。
https://cemt13.peatix.com
*申込期限終了後の申込につきましては事務局にお問合せください。
高校生・大学生発表セッションでの発表申込は上記Peatixに加えて以下フォームで発表内容をご入力ください。
https://forms.gle/WpkXh2LFWLV4Mf4Q9
■主催:日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)
(問合せ先)E-mail:jcef2013@gmail.com(担当:川中)
<個人情報の取扱い>
記載の個人情報は本セミナーの実施および今後の催事実施において、日本シティズンシップ教育フォーラムが利用します。個人情報は目的の範囲内で利用するとともに適切な方法で管理し、法令上の特段の事情がない限り、本人の同意なしに第三者への目的外での開示・提供はいたしません。
東京ミッドタウン・デザインハブ第118回企画展「公民館とデザインは、なにを夢みたのか?」展示組みあげメンバー募集
会員より、以下の募集がありましたので情報提供いたします。
------------------
「公民館とデザインは、なにを夢みたのか?」展の開催に先立ち、企画の主旨から展示会場そのものを社会教育的、デザイン的、さらには自治的にくみあげていくために、展示くみあげ期間を設定するとともに、主旨に賛同していただける皆さんをくみあげメンバーとして、募集します。
- 詳細:公民館のしあさってウェブサイトをご覧ください https://kominkan.world/2026/01/22/exhibition2026/
- くみあげ期間:2月9日(月) - 15日(日)
- 会場:東京ミッドタウン・デザインハブ
- 参加希望やお問い合わせ:https://kominkan.world/project/
東京ミッドタウン・デザインハブ 第118回企画展「公民館とデザインは、なにを夢みたのか? ~雑談がうまれる場所と、そのためのDesignをめぐって~」開催のお知らせ
会員より、参画企画のお知らせがありました。会場内でのトークやアクティビティも多く企画されています。詳しくは詳細URLからご覧ください。
----------------------------------------
東京ミッドタウン・デザインハブ 第118回企画展「公民館とデザインは、なにを夢みたのか? ~雑談がうまれる場所と、そのためのDesignをめぐって~」のご案内
基本情報:本展は、2023年3月に開催した、東京ミッドタウン・デザインハブ第102回企画展「公民館のしあさってはデザインのしあさって!?」に続く、社会教育とデザインに注目した企画展です。前回展からの積みのこしとも言える、「みんなで社会をくみあげる」という構想を実現するための方法やその主体などについて、公民館から社会教育に目線を上げ、その夢や希望に期待しながら、みなさんとともに考えてみたいと思います。
会期:2026年2月16日(月)~3月16日(月)11:00-19:00
会場:東京ミッドタウン・デザインハブ
休館日:なし
入場料:無料
共催:東京ミッドタウン・デザインハブ・公民館のしあさって・プロジェクト
企画・運営:公益財団法人日本デザイン振興会+公民館のしあさって・プロジェクト
後援:文部科学省・公益社団法人全国公民館連合会・公益財団法人トヨタ財団[申請中]
詳細:https://www.designhub.jp/exhibitions/kominkan2026
【申込期限の延長】ラウンドテーブル「社会教育施設概念のゆらぎを問う」開催のお知らせ(「会員のグループによる自主企画助成」による企画)
日本社会教育学会会員自主企画
ラウンドテーブル「社会教育施設概念のゆらぎを問う」開催のお知らせ
ーーーー
■申込み〆切延長のお知らせ(2026年2月1日):
会員・非会員問わず、2026年2月8日(日)23:59
但し定員に達し次第、先着にて受付を終了させていただきます
ーーーー
本企画は、2019年より実施してきたラウンドテーブル「社会教育法70年と社会教育法制をめぐる課題」(~2023年)および「社会教育施設概念の再検討」(2024年~)の延長線上に位置づけられるものです。
当初は、社会教育法70年を契機に社会教育法制に関する議論を進めてきましたが、その後の状況の変化を受け、社会教育施設をめぐる課題にシフトしながら、継続的に議論を深めてきています。
現在、社会教育施設をめぐって、所管を教育委員会から首長部局へ移管する動きが進むとともに、社会教育法を設置根拠としない施設も出現するなど、これまでの社会教育施設という概念そのものがゆらぎ始めており、その定義はもはや自明性を失いつつあります。
そこで本企画では、社会教育施設が置かれている状況や概念について整理したうえで、社会教育施設の輪郭をめぐる論点の洗い出しを行い、参加者相互の対話を通じて議論を深めることを目的とします。
また、ここで得られた成果を今後のラウンドテーブルに反映させていく予定です。
■ テーマ:社会教育施設概念のゆらぎを問う
■ 日 時:2026年2月11日(祝・水)13時30分~17時00分
■ 会 場:世田谷産業プラザ3F 小会議室 (※会場参加のみ)
東京都世田谷区太子堂2-16-7
https://maps.app.goo.gl/ra73fifg62KmSVcH7
■ 参加費:無料
■ 定 員:25名(※事前申込制)
※定員を超過した場合は会員を優先します。
※下記申込み〆切日を過ぎましたら、登録いただいたメールアドレスにご案内いたします。
■ 申込み:下記参加申込みフォームより事前にお申込みください
参加申込みフォーム https://forms.gle/Z3fZaKPWz7quHCUEA
※申込み〆切:2026年1月31日(土)23:59
■プログラム
これまでの取り組みについて(司会:金子淳会員)
報告① 社会教育法制と社会教育施設(生島美和会員)
報告② 公民館における論点整理(長澤成次会員)
報告③ 図書館における論点整理(石川敬史会員)
報告④ 博物館における論点整理(栗山究会員)
※本ラウンドテーブルは、日本社会教育学会「会員のグループによる自主企画助成」を受けて開催されるものです。
ラウンドテーブル「子ども・ユースワークをめぐる日独対話:子ども・若者の“第三の領域”とは?」の開催について
会員より以下の企画の案内がありました。参加登録は2026年1月18日(日)までです。
------------------
ラウンドテーブル「子ども・ユースワークをめぐる日独対話:子ども・若者の“第三の領域”とは?」
ユースワークを研究しているドイツの研究者3名(男性2名、女性1名)が日本に来てくれます。東京、京都、奈良の3会場でラウンドテーブル形式で意見交換をしながら論点を深めていければと考えています。
主な論点は、以下が想定されます。
・子ども・若者の状況を踏まえ、学校以外の場としてどのようなものが必要か?
・関わるスタッフはどう育ち、どのように支えられているのか?
・ユースワークの地域格差をどう乗り越えていくか?
・ドイツでの支援体制はどのように整備されているか?
ドイツでは、子ども・若者支援法(社会法典第8編)に基づき、27歳までの若者支援が権利として保障されている点、地方自治体・州・連邦の3段階の構造で公的部門と民間公益団体が協働で取り組みを進めている点(民間優位の補完性原理)、そのためスタッフの待遇を含めて官民格差や地域格差の小さい状況が確保されている点、地方自治体での子ども・若者支援委員会など民間公益団体の参画の仕組みが整備されている点、全国ユースワーク会議など子ども・ユースワーカーの全国組織が確立している点、青少年教育・福祉領域の学問としてのSozialpädagogik (social pedagogy) に関与する研究者の層が厚い点などが特徴としてあげられます。他方で、財政上の理由からカットされる施策や施設・センターの閉鎖、事業評価をめぐるせめぎ合いなどの問題も当然ながら課題としてあります。
ドイツ側からはパワーポイントでプレゼンもしてもらいながら、実践スタッフ、行政関係者、研究者、学生などのみなさんとゆっくりと意見交換・交流できればと思っています。
関心のある方は、下記の会場のラウンドテーブルへの参加登録をしてお越しください。参加登録は、以下のチラシのQRコードから1月18日(日)までにお願いします。
チラシ(日独ラウンドテーブル).pdf
東京都世田谷区:希望丘青少年交流センター・アップス :2月11日(水・祝日)13時-16時30分
京都市中京区:京都市ユースサービス協会中央青少年活動センター :2月14日(土)13時-16時30分
奈良市:奈良教育大学 寧楽館:2月16日(月)13時-16時30分
東京と京都ではユースセンターを使って開催します。奈良市では、 いつも不登校支援で使っている寧楽館(ねいらくかん: 奈良教育大学)で実施します。 通訳をはさんでの意見交換になりますがよろしくお願いします。
ところで、ドイツ側の問題意識は、 右派ポピュリズムや権威主義的な規範意識への対抗・批判と、 子ども・若者との交渉的・対話的プロセス、文化教育・ 活動のあり方の模索・追究にあります。
少し難しそうですが、 この取り組みを準備している企画チームで話題になったのは、 参院選などでの右派ポピュリズムの動向などとともに、映画「 小学校 それは小さな社会」(2023年、監督:山崎エマ、英題: The Making of a Japanese)です。英題にみられる通り、 日本人がどう作られていくのかに欧米でも関心が集まったようです 。他方では、この規範的、 権威的な行動様式と長時間の時間的拘束に対して、不登校・ 登校拒否などの形での回避、退却、リトリート、 別の回路の選択も見られます。こうした点も、 ラウンドテーブルで話題になりそうです。
なお、ラウンドテーブル以外に、 こども家庭庁や国立青少年教育振興機構、川崎市こども夢パーク、 文化学習協同ネットワーク(三鷹市)、 池田市水月児童文化センター、 奈良県三宅町ユースセンターなども訪問します。
本ラウンドテーブルは、日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)「子ども・ 若者支援従事者の専門性構築の課題と展望─「支援の重層性」 の視点から─」(研究代表者 生田周二:2022〜2025年度)の助成を受けています。
---------------
早稲田大学シンポジウム「なぜダイバーシティ教育を支える組織が大学に必要なのか」のご案内
日本社会教育学会関係各位
早稲田大学ジェンダー研究所・教育総合研究所の合同で、 下記の通りシンポジウムを開催いたします。
ぜひ多くの方にご参加いただき、 一緒にご議論いただければ幸いです。
記
2025年度早稲田大学ジェンダー研究所・教育総合研究所 合同シンポジウム
「なぜダイバーシティ教育を支える組織が大学に必要なのか」
日時:2025年12月20日(土)13時30分〜16時30分
場所:早稲田大学早稲田キャンパス8号館B107教室
申込:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHoLShkH7mavzr7nt8-MuWdePeTWSXsR03m9ilppelO8Eh3A/viewform
登壇者:西本あずさ( 青山学院大学スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター センター長)、田中真美(東北大学ダイバーシティ・エクイティ& インクルージョン(DEI)推進センター センター長・副学長)、秋林こずえ(同志社大学フェミニスト・ ジェンダー・セクシュアリティ研究(FGSS)センター センター長)、篠原初枝( 早稲田大学ダイバーシティ推進担当理事)、村田晶子( 早稲田大学)、弓削尚子(早稲田大学)
詳細:ジェンダー研究所ホームページ
https://waseda-gender-studies-inst.jimdofree.com/お知らせ-イベント-news-events-1/
2025年度 社養協 第1回定例研究会 「社会教育主事・社会教育⼠の養成のあり⽅に関する政策の最新動向」のご案内
日本社会教育学会 関係各位
全国社会教育職員養成研究連絡協議会(社養協)より、下記の研究会のご案内を頂きました。
なお、社養協の会員であるかを問わず、下記の研究会に参加いただけるとのことです。
***以下、転送文***
2025年度 社養協 第1回定例研究会
「社会教育主事・社会教育⼠の養成のあり⽅に関する政策の最新動向」のご案内
日頃より社養協の活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
第1回定例研究会「社会教育主事・社会教育⼠の養成のあり⽅に関する政策の最新動向ー中央教育審議会 ⽣涯学習分科会 社会教育の在り⽅に関する特別部会の動向についてー」のご案内をお送りいたします。多くの皆様にご参加いただけたら幸いです。
【趣 旨】中央教育審議会⽣涯学習分科会「社会教育の在り⽅に関する特別部会」および先⾏した「社会教育⼈材部会」における今後の社会教育主事・社会教育⼠の養成のあり⽅に関する議論と今後の社会教育法改正の可能性について、分科会の委員をされている牧野篤さんにお話をしていただき、参加者とともに今後の社養協の活動を議論していく契機としたい。
【日 時】2024年 7月 26日(土)14:00〜16:30
【会 場】明治大学 社会教育主事課程室 リバティタワー19階(17階でエレベータ乗り換え)
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
※オンラインでもご参加いただけます。
【報告者】牧 野 篤 ⽒(⼤正⼤学教授,中央教育審議会⽣涯学習分科会委員)
【申 込】 7⽉ 24⽇(⽊)までに以下のフォームからお申し込みください。
https://forms.office.com/r/3CZHn0uvyZ
【チラシ】第1回定例研究会チラシver2.pdf
立教大学文学部教育学科公開講演会のお知らせ
立教大学文学部教育学科公開講演会(対面のみ)
https://www.rikkyo.ac.jp/events/2025/04/mknpps0000034jyf.html
いま、韓国の民主主義はどうなっているのだろうか?
ー3人の韓国人女性社会教育・生涯学習研究者が語る!ー
近年、日本では、韓国の民主化をテーマにした映画が上映され、大きな話題を呼んでいる。その背景には、停滞する日本の民主主義からの脱却を、韓国の民主化経験に学ぼうとの姿勢があるように思われる。2016年のキャンドルデモで、当時の朴槿恵大統領を退陣に追い込んだ光景は記憶に新しい。そうであるからこそ、2024年の尹錫悦大統領による戒厳令の宣言によるクーデター未遂は衝撃的であった。それと同時にクーデターを身体を張って阻止した「市民」の姿に、韓国の民主主義の底力を感じることになった。
民主主義を根本から支えるのは教育である。だが、韓国では日本以上に競争的な学校教育が展開している。ならばどこに「市民」が育つ場所や文化があるのか。本講演会では、韓国の民主主義の現在とそれを支える政治文化や市民意識について、社会教育・生涯学習を専門とする3人の韓国人女性研究者が語り合う!
日時:4月12日(土)14時〜17時
場所:立教大学池袋キャンパス マキムホールM202教室
講演者:李 正連氏(東京大学大学院教育学研究科教授)
呉 世蓮氏(関東学院大学国際文化学部准教授)
金 亨善氏(東北大学高度教養教育・学生支援機構学術研究員)
李正連氏には韓国の市民社会と民主主義の現在史を、呉世蓮氏には1980年の光州事件後に光州が独自に行ってきた民主市民教育と今回の戒厳に対する光州市民の反応を、金亨善氏には日韓の若者文化の比較から韓国社会の現状を話していただく。
主催:立教大学文学部教育学科
対象:学部学生、大学院生、教職員、一般
事前申し込み(Googleフォーム):https://forms.gle/a3c5UFbRVQ5XfKRg6
問い合わせ:立教大学文学部教育学科教授 和田 悠
2024自由大学運動100周年記念フォーラム「自由大学運動100年から学ぶ『未来へ』」ご案内
日本社会教育学会 関係各位
2024自由大学運動100周年記念フォーラム「自由大学運動100年から学ぶ『未来へ』」ご案内
2022年集会(東京・上田)・2023年集会(上田)に続く一連のフォーラムの最終年となります。
日時:2024年11月10日(日)9時15分〜16時30分(受付9時〜)
場所:上田商工会議所(5階ホール)
https://www.ucci.or.jp/access/
内容:・基調講演:長島伸一(長野大学名誉教授)「自己教育と相互主体的な学びを創る」
・ゼミナールの試みと体験「私たちが目指すゼミナールってどのようなもの?」
(1)何のために学ぶのか (2)子どもの成長を考える (3)いのち (4)老後の楽しみ
参加費:500円 ※高校生以下は無料
昼食お弁当は別途1,000円(要申込)
頒価2,000円で2022年上田集会の記録集を購入いただけます
定員:100名(定員に達し次第締切り)
申込み:11月5日(火)までに氏名、住所、連絡先、昼食弁当の有無、午後の部の参加希望テーマ((1)(2)(3)(4))を明記して下記実行委員会事務局までメールで申込み
申込み・問合せ:自由大学運動100年記念フォーラム実行委員会事務局
(有限会社伸和印刷内)nakazawa◎p-shinwa.co.jp ※◎を@に変更
共催:上田市教育委員会
→詳細はこちら(上田市HP内、チラシもこちらから)
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/99596.html
日本教育学会北海道地区企画公開シンポジウムのお知らせ
日本社会教育学会 関係各位
【日本教育学会北海道地区企画公開シンポジウム】
学校・地域・居場所をどう組み直すか
■日時:2024年6月30日(日)10時〜13時
■場所:北海道大学人文社会科学総合教育研究棟(W棟)103室
■参加:無料(どなたでも)
※対面参加は申込不要、オンライン参加は要申込
⇒オンライン参加方法および問い合わせ先は添付チラシ参照
■プログラム
○問題提起
「公教育と居場所をめぐる状況と検討課題」横井敏郎会員(北海道大学)
○報告1
「学校支援からローカル・コモンズへ〜居場所と学校」青砥恭氏(NPO法人さいたまユースサポートネット)
○報告2
「自分が“世界”と出会う場所〜学校は小さなまち〜」井内聖氏(北海道安平町教育委員会教育長)
○報告3
「居場所の政策化と学校・地域への役割の期待についての検討」阿比留久美会員(早稲田大学)
○司会:辻智子会員(北海道大学)
関心ある皆さんのご参加をお待ちしています。
(主催:日本教育学会北海道地区(理事:辻智子、横井敏郎))
九条俳句十周年記念集会『今、表現の自由を問う 九条俳句事件から10年──』のご案内
日本社会教育学会 関係各位
九条俳句十周年記念集会が、埼玉大学にて、下記の通り、開催されます。
ぜひ日本社会教育学会からも多くの会員の皆様にご参加いただけますよう、よろしくお願いします。
詳細については、下記の添付チラシのPDFファイルをご参照ください。
____________________________
九条俳句十周年記念集会『今、表現の自由を問う 九条俳句事件から10年──』
九条俳句事件から10 年。上告棄却、東京高裁勝訴判決確定から5 年。あらためて、この17 文字の持つエネルギーと訴訟の意味や役割を今の社会に考えてみます。そして今こそ社会教育や公民館活動の活性化を市民で再獲得、真の「表現の自由」を私たちのものにしましょう。どうぞどなたもご参加ください。
日 時 2024 年 6月29 日(土)13:00 ~ 16:30
場 所 埼玉大学教育学部C1 講義室 (〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255)
主 催 九条俳句訴訟を今につなぐ市民の会
後 援 さいたま市/ さいたま市教育委員会/ 日本社会教育学会/ 日本公民館学会/
社会教育推進全国協議会/ 表現の自由を市民の手に全国ネットワーク
参加費 800 円 学生・障害者無料(終了後ミニ交流会があります)
〈第1部〉10年のあゆみを振り返る
ビデオ上映〈九条俳句事件闘争小史〉
弁護団、応援団、作者からのスピーチ
記念講演 佐高 信さん(評論家)「反戦川柳人 鶴彬〈つる・あきら〉と九条俳句事件」
〈第2部〉表現の自由を巡る各地の取り組み
コーディネーター
● 石川智士さん《元九条俳句訴訟弁護団》
パネリスト
● 神田香織さん《講談師:ヒロシマ、はだしのゲン、群馬の森から何を 》
● 溝口一郎さん《九条の会・ちがさき:茅ケ崎市の後援拒否問題で横浜地裁提訴》
● 米山義盛さん《飯田市平和祈念館を考える会》
● 武内暁さん《九条俳句市民の会:表現ネットの今後は 》
● 会場から(各地からの報告)/ アピールなど
学校部活動のオルタナティブとしてのボーイスカウトと青少年赤十字の可能性第3回研究会のご案内
日本社会教育学会 関係各位
本研究会は、ボーイスカウトや青少年赤十字に代表される子どもの社会教育団体が学校 部活動のオルタナティブとなる可能性について、学会内外から話題提供者を招き、実践者も交えてディスカッションすることを目的としています。2021年から中学校の部活動を段階的に地域へ移行する施策が進められているところですが、スポーツクラブ・民間事業者への移行だけで、子どもの多様で豊かな経験機会を確保できるでしょうか。
第3回は、これまでにおこなった研究会の総括と展望についてまとめる回とします。第1 回、第2回の振り返り、ここまでに見えてきた具体的なことがらを踏まえ、そのうえで、全体で意見交換したいと思いますので、これまでの参加者の方だけでなく、今回はじめての方もぜひご参加ください。
日 時:2024年3月29日(金)19時30分〜21時00分
場 所:オンライン
参加申込:3月28日(木)までに申込みフォームから送信してください。参加のための情報を当日までにお送りします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEKOBJZab98UbuIBe4oAiz04tvEdSrRSpZC2EqGb1vsXg6xQ/viewform
企 画 者: 松岡 悠和(京都府立大学大学院)、高橋 健(北海道日高高等学校)、鎌田 宜佑(九州大学大学院)、 圓入 智仁(中村学園大学)
本件に関する問合せ先: mtokyw [at] gmail.com (松岡)(※[at]を@に変えてください。)
社養協 2023年度第2回研究会開催のお知らせ
2024年1月17日
日本社会教育学会 御中
全国社会教育職員養成研究連絡協議会
代 表 村 田 晶 子
2023年度第2回研究会「社会教育実践の交流ラウンドテーブル」の開催について(通知)
日ごろから、全国社会教育省育職員養成研究連絡協議会(社養協)の活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 標記研究会につきまして、下記の通り開催いたします。研究会趣旨、申し込み方法など、詳細につきましては、添付のチラシをご覧ください。
ご多忙とは存じますが、ぜひご参加いただきますよう、どうぞよろしくお願いします。
記
全国社会教育職員養成研究連絡協議会
2023年度第2回研究会「社会教育実践の交流ラウンドテーブル」
【日 時】2024年2月4日(日)9:30〜12:00
【開催方法】Zoomによるオンライン形式
【プログラム】
9:30 開会あいさつ
9:35 ラウンドテーブルの意味・趣旨説明
9:40 話し合いのルール説明
9:50 グループでの自己紹介(または報告)
10:30 グループ 報告と意見交換
11:30 全体でふり返り
12:00 終了(アンケートフォームに入力)
【申 込】 1月31日(水)までに以下の申込みフォームからお申し込みください。
※開催の数日前までに、申し込みいただいたメールアドレスに参加方法等をお送りいたします。
https://forms.office.com/r/u0ACj07LAS
【問合せ】全国社会教育職員養成研究連絡協議会(社養協)事務局
〒632-8510 奈良県天理市杣之内町1050 天理大学 杉山晋平研究室
電話 0743-63-8198
Email shayosei◎outlook.com (◎は@に変えてください)
※詳細は添付ファイルをご覧ください。
【参加募集】 1/19~21「ユネスコウィーク2024」イベントを開催します!
日本社会教育学会 関係各位
ユネスコ未来共創プラットフォーム事務局(ユネスコ・アジア文化センター(ACCU))では、今年度も「ユネスコウィーク」を開催します。ユネスコとユネスコの活動についての知識を深めたいと考えるユースや、地域のユネスコ活動を主導する関係者の方々、持続可能な開発目標(SDGs)の実現へ向けてパートナーシップの強化に取り組む実務者まで、幅広い層の方々からのご参加をお待ちしております!
|
ユネスコウィーク2024「共に創造する未来 ~ユネスコ活動によるアプローチ~」 会場 国立オリンピック記念青少年総合センター ※Web配信あり 参加費 無料 主催 文部科学省、日本ユネスコ国内委員会 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター 共催 国連教育科学文化機関(UNESCO)(予定) 申込み 特設サイトよりお申込みください https://unesco-sdgs.mext.go.jp/unesco-week-2024 |
【イベント詳細】
国際シンポジウム「共に創造する持続可能な未来」
日時 2024年1月19日(金) 18:00~19:30
言語 日本語・英語(同時通訳)
<内容>
「共に創造する未来」を考える上で、どのような分野横断的な取組が有効なのか-国内外の実践事例をもとに議論を深めます。基調講演者にはDzulkifli bin Abdul Razak氏(マレーシア国際イスラム大学学長)をお迎えします。ESDに関する様々な国際会議で登壇経験をお持ちのRazak氏の講演を、日英同時通訳でお聞きになる大変貴重な機会です。
第15回ユネスコスクール全国大会「未来のユネスコスクールを考える-ASPnet70周年を迎えて-」
日時 2024年1月20日(土) 9:30~17:00
言語 日本語 ※一部日英同時通訳の分科会を含みます
<内容>
ユネスコスクールの意義・役割や国内外のユネスコスクールをめぐる動向について学び、また優良事例の共有や関係者間の交流を図ります。特に今回はユネスコスクール発足 70 周年の節目として、これまでのユネスコスクールの歴史や成果・課題を振り返り、今後を展望するような内容となっています。
ユースフォーラム「ユースによる『未来への宣言』〜ユネスコ活動から考える気候変動〜」
日時 2024年1月21日(日) 10:30~16:00
言語 日本語
<内容>
気候変動に焦点を当て、ユネスコ活動を通じた気候変動問題への対応及びユース世代が果たすべき役割について再考します。また、「未来への宣言」策定へ向けた参加型ワークショップも実施しますので、若者の声を届けるべく、是非ユース世代の積極的なご参加をお待ちしています。当日は、兵庫県芦屋市の髙島市長からもオンラインの応援メッセージをいただきます!!
※イベントの詳細は、下記の添付ファイルを参照ください。
かわさき市民アカデミー開学30周年記念シンポジウム 「新しい時代の市民大学」のご案内
日本社会教育学会 関係各位
かわさき市民アカデミー開学30周年記念シンポジウム
「新しい時代の市民大学」
(1)日時:12月9日(土)13:00~16:00
(2)場所:川崎市生涯学習プラザ4階大会議室(武蔵小杉駅から徒歩10~15分)
https://www.kpal.or.jp/9_annaizu/911_zaidan_plaza_annai.html
(3)概要:
①基調講演:坂口緑(明治学院大学教授)「新しい時代の市民大学」
②パネルディスカッション
【コーディネーター】田中雅文(日本女子大学名誉教授)
【パネリスト】坂口緑(同上)、澤野由紀子(聖心女子大学教授)、大澤悠季(NPO法人シブヤ大学学長)、馬場康雄(かわさき市民アカデミー学長)
(4)参加形態:会場参加、オンライン参加のどちらも可能
(5)申込・問合:添付のチラシご参照 かわさき市民アカデミー シンポジウム.pdf
社養協2023年度研究大会「社会教育実習におけるハラスメントの防止」の開催のご案内
日本社会教育学会 関係各位
2023年度研究大会「社会教育実習におけるハラスメント防止」の開催について(通知)
日ごろから、全国社会教育職員養成研究連絡協議会(社養協)の活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 標記研究大会につきまして、下記の通り開催いたします。研究大会趣旨、申し込み方法など、詳細につきましては、添付のチラシをご覧ください。 社養協2023年度研究大会チラシ.pdf
ご多忙とは存じますが、ぜひご参加いただきますよう、どうぞよろしくお願いします。
記
【日 時】2023年12月23日(土)10:00〜12:00
【開催方法】Zoomによるオンライン形式
【プログラム】1.報 告:「教育実習におけるハラスメント防止の現状と課題」
内海崎 貴子さん(白百合女子大学)
2.情報交換:社会教育実習におけるハラスメント防止の取り組み
司会:野元 弘幸(東京都立大学)一盛 真(大東文化大学)
【申 込】 12月20日(水)までに以下の申込みフォームからお申し込みください。
※開催の数日前までに、申し込みいただいたメールアドレスに参加方法等をお送りいたします。
https://forms.gle/hPnmvv6MQgccRUwU7
2023自由大学運動100周年記念フォーラム(上田集会) 「自由大学運動100年から学ぶ 過去・現在・未来」
日本社会教育学会 関係各位
2023自由大学運動100周年記念フォーラム(上田集会)
「自由大学運動100年から学ぶ 過去・現在・未来」
昨年集会に引き続き、長野県上田市にてフォーラムを開催します。
若手会員のみなさまの参加を心よりお待ちしております。
日時:2023年11月26日(日)9時20分~16時30分(受付9時~)
場所:上田商工会議所(5階ホール)
https://www.ucci.or.jp/access/
内容:午前の部
シンポジウム「わたしと自由大学」4名の発表
1.城田美好(早稲田大学大学院博士後期課程)
「現代社会に取り戻す相互主体性・民主主義・平和の連続性」
2.佐々木七美(一橋大学大学院博士後期課程)
「〈学校教育〉という近代的価値観をときほぐす」
3.小池貴博(東京都私立中学校・高校非常勤講師)
「学び手と教え手、双方の視点から捉えた教育的関係性」
4.栗山究(法政大学等非常勤講師)
「上田自由大学と地域博物館」
午後の部
グループワーク「あなたと自由大学」
参加費:500円 ※大学生以下は無料
昼食弁当は別途1,000円(要申込)
別途1,500円で昨年度の上田集会の記録集を購入いただけます
定員:100名(定員に達し次第締切り)
申込み:11月20日(月)までに氏名、所属、住所、連絡先、学割の有無、
昼食弁当の有無、グループワークのファシリテーター経験の有無を
明記して下記事務局までメールで申込み
申込み・問合せ:自由大学運動100年記念フォーラム実行委員会
(有限会社伸和印刷内)nakazawa◎p-shinwa.co.jp ※◎を@に変更
共催:上田市教育委員会
→詳細はこちら(上田市HP内、チラシもこちらから)
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/85225.html
東アジア生涯学習研究フォーラム in 名護 2023 のご案内
日本社会教育学会 関係各位
下記の通り、東アジア生涯学習研究フォーラム in 名護 2023を開催致します。
なお、詳細に関しては、添付ファイルをご覧ください。
2023.1002東アジアフォーラム in 名護開催要項.pdf
東アジア生涯学習研究フォーラム in 名護 2023 開催要項
テーマ
集落・社区・マウルの自治と生涯学習政策
主 催
・文部科学省科学研究費 学術変革領域研究(A)計画研究「生涯学習計画に関する国家政策
および地域主導計画の東アジア的視座からの検証」(20H05808)(研究代表者・石井山竜平)
・東京・沖縄・東アジア社会教育研究会(TOAFAEC)(代表:上野景三、顧問:小林文人)
開催日
2023 年 11 月 19 日(日)~21 日(火)
会 場
沖縄県名護市〔屋部公民館(19 日)、名護博物館(20 日)、等〕
参加者
日本、韓国、中国、台湾の社会教育・生涯学習研究者。定員 70 名。
(日中、日韓、韓中の通訳を用意しております。)
参加費
無料 (交通費・宿泊費等は自前でご対応ください。なお、各施設入館料、昼食費、懇親会
費等を別途徴収いたします。)
内 容
11 月 19 日(日) 屋部公民館
・午前:「生涯学習をめぐる政策ないし実践的動向の新展開」
中国・韓国・台湾・日本のそれぞれからの報告、全体協議。
・午後:「『人間の一生』の新段階と生涯学習政策」
「人間の一生涯における学習条件をいかに整えるのか」をめぐる近年の重要な研究成果
を、中国・韓国・台湾のそれぞれから一本ずつ、学領域を限定せず、最新の研究動向から
話題提供をしていただく。
・夜 :懇親会 ホテルゆがふいんおきなわ
11 月 20 日(月) 名護博物館(2023 年 4 月オープン)
・午前 シンポジウム「ぶりでぃ(群り手)で地域を元気に-名護の社会教育-」
ご登壇者 稲嶺 進 氏(前名護市長)
島袋正敏 氏(初代名護博物館館長・元名護市教育次長)
比嘉 久 氏(名護博物館特任館長)
司会・総括 小林文人 氏(東京学芸大学名誉教授)
・午後 パネルディスカッション「集落・社区・マウルの自治と生涯学習政策」
中国・韓国・台湾・日本から、本国の状況報告も含めてコメント。
・夜 :懇親会 城公民館
11 月 21 日(火)エクスカーション
8:30 ホテルゆがふいんを出発
12:30 佐喜眞美術館
丸木位里・丸木俊夫妻の「沖縄戦の図」の鑑賞(解説:佐喜眞道夫館長)
海勢頭豊氏の歌と演奏
15:00 解散
参加受付方法
日本からの参加者は、応募フォームより、求められる内容を記載の上、お申し込みくださ
い。事務局より受理の連絡の上、参加登録となります。
参加申し込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGat88ohGy3hCAdWMlDpHYWbAAMqB7
5kc5Uq0lNC2GTZRtSA/viewform
参加受付期間
~2023 年 10 月 18 日(水)
その他
・全プログラム(懇親会を含む)への参加を原則といたします。ご参加いただく方々には、
ディスカッションや懇親の席で、適宜、コメントをいただきます。
・初日懇親会会場となるホテルゆがふいんの宿泊条件 (11 月 19 日~21 日)を若干確保しております。
ご希望の方は、応募フォームよりご相談ください。
本事業に関するお問い合わせ先
石井山竜平(東北大学) ishiiyama◎hotmail.com ※◎を@に変更
法政大学によるオンラインシンポジウムのご案内
日本社会教育学会 関係各位
下記の通り、法政大学より、下記のオンラインシンポジウムの開催案内を頂きましたので、転送いたします。
***
法政大学大学院キャリアデザイン学研究科では10月14日(土)に、オンラインによるシンポジウム・進学相談会を開催いたします。
今日、「リカレント教育」があらためて注目を集めています。「リカレント教育」は、今の仕事を深めるための学び、新たな職業に向かうための学び、あるいは自己を掘り下げるための学び、地域や社会とつながっていくための学びなど、さまざまな「学び」と結びつけて考えることができます。今回のシンポジウムでは、社会経済的観点と個人のウェルビーイングの観点から、今後のリカレント教育のあり方を展望したいと思います。
(なお、プログラム1の後半、およびプログラム2は、本大学院進学希望者向けの内容となります。プログラム1の前半だけ参加されるという方ももちろん歓迎いたします)
【開催概要】
日程: 10月14日(土) 13:00~16:00
時間: 以下の通り
形式: Web会議ツール「Zoom」によるオンライン開催
※ 内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。
※ 時間は当日の進行や申し込み状況により、若干前後する可能性があります。
《プログラム1 13:00~14:50》
■シンポジウム(13:00~14:15)
「リカレント教育の今日的課題―社会経済的観点と個人のウェルビーイングの観点から―」
開会挨拶
廣川進(法政大学キャリアデザイン学研究科 研究科長・教授)
話題提供
岩崎久美子(放送大学教養学部 教授)
コメント
佐藤厚(法政大学大学院キャリアデザイン学研究科 教授)
久井英輔(法政大学大学院キャリアデザイン学研究科 教授)
■修了生による体験談(14:20~14:50)
古川遼氏(コーンフェリージャパン株式会社)
林雅子氏(アサヒグループジャパン株式会社)
《プログラム2 15:00~16:00》
■大学院進学相談会(15:00~16:00)
進学に関するご相談や、当研究科の授業・学習等についてのご質問に、キャリアデザイン学研究科の専任教員がお答えします。
※複数の志願者と同時に相談を行う公開相談会形式での開催となります。(個別相談形式ではありません。)
※当日相談できる内容は「研究科・専攻について」「授業内容について」「研究内容・計画に関する相談」等です。「受験資格の有無」「出願書類・証明書の用意」等といった事務手続きや奨学金・助成金制度については当日の回答ができない場合があります。これらについては本ページ末尾の「お問い合わせ先」からお問い合わせください。
【備考】
事前申し込みが必要です。
法政大学 大学院事務部大学院課
E-mail:soudankai◎ml.hosei.ac.jp ※◎を@に変更
(〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-15-2
TEL:03-5228-0551)
申込み〆切: 10月10日(火) 15:00
以下の大学ホームページの掲示もご参照ください。
https://www.hosei.ac.jp/gs/info/article-20230719081012/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
若者の市民活動を考えるシンポジウムの開催
日本社会教育学会 関係各位
若者の市民活動を考えるシンポジウムを開催します(詳細は下記URLご参照)。
市民活動の若き担い手たち.pdf
(1)テーマ:未来をひらく学び Part2 ―市民活動の若き担い手たち―
(2)日時:9月23日(土・祝)14:00~16:00
(3)場所:武蔵野市立かたらいの道市民スペース
(4)概要:学生ボランティア団体(4団体)と若手職業人の市民活動者(2人)が活動への取組みや想いを語り、若年層における市民活動の輪を広
げる可能性をみんなで考えます。
(5)申込:先着順50名まで(下記からお申込みください。Zoomによる参加も可。)
https://forms.gle/XZCuydyetmMzhZPk9
(6)問合せ:田中雅文まで(メール: tanaka95◎jcom.zaq.ne.jp)※◎を@に変更
オンライン・シンポジウム『若者が集える地域づくりと大学の役割』
日本社会教育学会 関係各位
オンライン・シンポジウム『若者が集える地域づくりと大学の役割』
主催:科研・基盤研究(B)「高大接続と大学初年次教育の思想・実践的研究」グループ
共催:J-CEF・高大接続及び大学初年次教育からみた主権者教育のあり方をめぐる研究グループ
日時:2023年7月29日(土)14:00-16:00
会場:オンライン(zoom)
申込:事前登録制。以下フォームもしくは、QRコード(添付ファイル参照)からお申し込みください。
https://forms.gle/f28KzvRfZtW6Enu69
内容:
第1部 報告 14:00〜15:00
講師
土肥 潤也 (NPO法人わかもののまち代表理事、こども家庭庁こども家庭審議会 委員)
「高校生から大学生への連続的な社会参画機会の構築」
笠原 活世 (菊川市市民協働センター長)
「若者の力:菊川市における社会参画と地域貢献」
第2部 討論 15:00〜16:00
討論者
小玉 重夫 (東京大学大学院教育学研究科・教授 専門は教育哲学)
両角亜希子(東京大学大学院教育学研究科・教授 専門は大学経営論)
司会
井柳 美紀 (静岡大学人文社会科学部法学科・教授 専門は政治学)
問い合わせ先:井柳 美紀(iyanagi.miki◎shizuoka.ac.jp)※◎を@に変更
詳細については、下記の添付を参照ください。
「若者が集える地域づくりと大学の役割」シンポジウム.pdf
シンポジウム「子ども・若者の目線で社会のあり方を考えよう」のご案内
一般社団法人日本社会教育士会
2022年度シンポジウム「子ども・若者の目線で社会のあり方を考えよう」開催案内
子ども・若者が生き難さを抱え様々な困難に直面していると報じられて
います。
こうした状況に対して社会教育は、どのようなことに取り組んでいけば
よいのでしょうか。
今年度のシンポジウムでは、全国各地で子ども若者のために実践に取り
組んでいる方々からその実践を報告していただき、地域の社会教育実践
についてや社会教育士、社会教育職員のあり方を考え合うシンポジウム
を開催します。
ぜひご参加くださいますようお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日時:2023年2月17日(金)19時30分から21時30分
開催方法:オンライン
パネリスト:小野寺玲さん(福井スコーレ)
渋谷幸靖さん(特定非営利法人陽和)
ファシリテーター:大村惠さん(愛知教育大学・日本社会教育士会理事)
参加費 :会員無料、一般 1000円、学生500円
申込 :一般社団法人日本社会教育士会 | Peatix (http://ptix.at/uuvhT9)
詳細 :当会ホームページ (https://onl.la/nYEHY7s)をご覧ください
※お申し込みの皆様には、後日、Zoomの接続情報をお知らせいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご案内「東アジアの友情形成と草の根の学び」
日本社会教育学会 関係各位
会員の阿知良と申します。
関心のある方にご参加いただけたらうれしく思い、この場を借りてご案内申し上げます。
「東アジアの友情形成と草の根の学び」
趣旨 ウクライナ情勢・東アジア情勢を前に、軍拡が世論を覆っています。
しかし、草の根の学びの中には、軋轢・対立は対話によって解決の道を探ることができると確信を掴み実践してきた蓄積があります。
北海道・朱鞠内では国境を越えた若者たちが集い、アジア太平洋戦争中の強制労働犠牲者の遺骨の発掘を通じて友情を形成してきました。
その舞台となった笹の墓標展示館が雪で倒壊しましたが、その再生活動を次の世代が中心になって行っています。
再生活動の事務局を担う金英鉉さんに学び、現在の情勢下での草の根の対話と学びの価値を再検討したいと思います。
■日時:2月4日(土)19:00~20:30
■場所:zoom 定員30名 無料
■報告者:金英鉉さん(笹の墓標再生実行委員会事務局)
■笹の墓標展示館の活動についての参考HP https://www.sasanobohyo.com/
■参加申し込み:締め切り2月3日(金)18:00 achiray◎mmm.muroran-it.ac.jp(阿知良洋平、◎を@に変更)まで、氏名、所属、メールアドレスを連絡ください。当日の朝までにzoomのアドレスを送ります。
■世話人 阿知良洋平、栗山究、浪指拓央、萩原達也
■問い合わせ先:阿知良洋平 achiray◎mmm.muroran-it.ac.jp ※◎を@に変更
第1回鹿児島大学リカレント教育シンポジウムのお知らせ
日本社会教育学会関係各位
この度、社会人向けの教育プログラムの開発とその実施体制の確立を目的に、「第1回 鹿児島大学リカレント教育シンポジウム」を下記日程の通り開催いたします。
ご多忙中大変恐縮ではございますが、貴部局の教職員・学生へのご参加およびご周知方、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
記
【日 時】 令和4年11月5日(土)13:00~16:00
【開催場所】 郡元キャンパス 農・獣医学部共通教育棟101
【参加費】 無料
【申込方法】 鹿児島大学高等教育研究開発センター
生涯学習部門HPよりお申込み下さい。
https://www.life.kagoshima-u.ac.jp/
※申込締切:11月1日(火)16時
⇒締切の記載は1日となっておりますが、11月4日に延長することになりました。(追記)
【問合せ先】 高等教育研究開発センター・生涯学習部門 中村・水谷
099-285-7122(内戦7122)
どなたでも参加いただけるシンポジウムです。
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
なお詳細は、下記の添付ファイルを参照ください。
全国障がい者生涯学習支援研究会のご案内
日本社会教育学会 会員の皆様
下記の通り、研究集会の案内がありましたので、転送いたします。
********
会員の寺谷直輝(@愛知)と申します。
全国障がい者生涯学習支援研究会が主催している研究集会の案内を情報共有いたします。
興味のある方は、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。
日 時:2022年12月4日(日) 10:00〜16:00
(開場 9:30)
場 所:愛知県立大学サテライトキャンパス(ウインクあいち15階)
内 容:課題研究「障害者生涯学習政策5年間の検証」
研究発表
定 員:50名(申し込み先着順) ※定員となり次第、受付終了となります。
参加費:会員4,000円(一般5000円)
★研究誌7号代と送料を含みます。
参加費は当日受付にてお支払いください。
参加申込:以下のフォームに記入・送信をお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQsCh__SST7Gxt200QCvAn3mIvh-1UeuZK4kDr46G6Q_EiQ/viewform
HPはコチラです!
https://sss-kenkyu.jimdofree.com/
ー---------------------
<プログラム>
(日時)2022年12月4日(日)10:00-16:30
(開場 9:30)
(場所)愛知県立大学サテライトキャンパス(ウインクあいち15階)
司会:水野和代(日本福祉大学講師)
10:00〜10:10 あいさつ
田中良三(愛知県立大学名誉教授)
<課題研究>
(テーマ)障害者生涯学習政策5年間の検証
司会:京 俊輔(島根大学准教授)
小林洋司(日本福祉大学准教授)
10:10〜11:30【前半】発表20分+質疑10分
①文部科学省の立場から
鈴木規子(文部科学省障害者学習支援室室長)
②政策支援の立場から
津田英二(神戸大学教授)
③実践研究委託事業から
田中良三(愛知県立大学名誉教授)
11:30〜12:20 <昼食・休憩>
12:20〜12:50 総 会
議長:寺谷直輝(大同大学他非常勤講師)
12:50〜14:50【後半】発表20分+質疑10分/全体討論50分・まとめ10分
④障害者生涯学習研究から
小林 繁(明治大学教授)
⑤社会教育・生涯学習研究の立場から
辻 浩(名古屋大学教授)
★全体討論・まとめ
<研究発表> 発表20分+質疑10分
司会:田中隆人(立命館大学大学院博士後期課程)
15:00~15:30 「余暇活動と学び」
田中克也(地域活動支援センターdeco boko BLUES代表)
15:30~16:00 「地域における障害者の生涯学習支援の構築-春日井市における民間と行政の連携・協働による体制づくり-」
志村美和(春日井子どもサポートKIDS COLOR代表)
なお、詳細については、下記の添付資料もあわせて参照ください。
国立女性教育会館(ヌエック)・ 男女共同参画センターに関する 緊急連続学習会のお知らせ
日本社会教育学会 会員各位
政府は本年6月に「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022(女性版骨太の方針2022)」を発表しました。
その中で、国立女性教育会館(ヌエック)の所管を文部科学省から内閣府に移管することが打ち出されました。
また、各地の男女共同参画センターについて、その機能の強化・充実をはかるとともに、それらを「束ねる」拠点としてヌエックの機能を強化する、との内容も盛り込まれました。社会教育の研究・実践にかかわってきた者として私たちは、この方針をどのように受けとめればよいのでしょうか。これを考えるにあたり、ヌエックや男女共同参画センター等について、これまでの経緯や現状を知り、今後の役割について議論する場を、急きょ、設けることにしました。皆さんのご参加をお待ちしております。
第1回 2022年10月10日 19時30分~21時30分 国立女性教育会館(ヌエック)とは
第2回 2022年11月8日 19時30分~21時30分 男女共同参画センターの学習・教育事業の現状と課題
第3回 2022年11月28日 19時30分~21時30分 女性関連施設/社会教育施設等の担い手の現状と課題を考える
なお、申し込み先・連絡先などの詳細に関しては、下記のファイルを参照ください。
『グローバル エデュケーション モニタリング レポート 2021/22 教育における非政府アクター』ローンチウェビナーのご案内
SDG4(教育目標)の進捗状況ならびに今年のレポートのテーマである「教育における非政府アクター」についての市民・学生の理解を促進するとともに、SDG4の達成に向けた日本のODAおよびNGOの役割について考えるためのウェビナーを下記の通り開きます。どなたでもご参加いただけます。
・共催: 広島大学教育開発国際協力研究センター(CICE)、国際協力機構(JICA)、ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)、 教育協力NGOネットワーク(JNNE)、UNESCO Global Education Monitoring Report、ユネスコ・アジア太平洋地域教育局
・協力: (公社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
・日時: 2022年6月30日(木)16:00-18:00
・開催方法: Zoomウェビナー版を使って実施します。Zoomの情報は申し込みをされた方に折り返しお送りします。
・プログラム:
16:00-16:05 開会
16:05-16:10 開会挨拶 青柳 茂 ユネスコ・アジア太平洋地域教育事務局・バンコク事務所長
16:10-16:40 「『GEMレポート2021/22』の概要と私たちへの問いかけ」
吉田和浩 広島大学教育開発国際協力研究センター教授
16:40-17:55 パネルディスカッション 「SDG4達成における非政府アクターの役割 ーコロナ禍時代における国際教育協力」
進行:大安喜一 ユネスコ・アジア文化センター教育協力部長
パネリスト:
1. 國枝信宏 JICA国際協力専門員 「コミュニティと学校の協働~「みんなの学校」を事例に」
2. 関本保孝 元東京夜間中学教員「国の夜間中学増設方針と夜間中学映画『こんばんはⅡ』の全国上映キャラバンの取組」
3. 企業関係者 未定
4. 村上友紀 Global Education Monitoring Reportチーム、プロジェクト・オフィサー 「2021/2 GEMレポートの中核的な発見と提言の発表」
5. 三宅隆史 教育協力NGOネットワーク事務局長 「難民の教育保障における非国家組織ならびにNGOの役割」
質疑応答
コメンテーター:萬理加 ユネスコ・アジア太平洋地域教育局所長室長 兼 アジア太平洋地域教育事業コーディネーター
17:55-18:00 閉会挨拶 佐久間 潤 JICA人間開発部長
・参加者:280名(先着順で定員になり次第締切ます)
・参加費:無料
・申込は、オンラインで下記からお願いします。https://ssl.form-mailer.jp/fms/2c578dbf582582
・GEMレポート2021/22要約の日本語版は、https://cice.hiroshima-u.ac.jp/?p=9846 からダウンロードできます。
・なお、登録時に提供する情報は、共催団体と共有され、主催団体は、その情報を団体のプライバシーポリシーに従って使用できます。
・お問い合わせ:教育協力NGOネットワーク 三宅隆史までメール jnne◎sva.or.jp でお願いします。(※◎を@に変更)
 社会教育研究読書会の開催に関するご案内
社会教育研究読書会の開催に関するご案内
社会教育研究読書会の開催に関するご案内
はじめまして。東京大学大学院の執行と申します。
わたしたちは、大学院生を中心として、有志で社会教育研究の重要文献・古典等を扱う読書会を行ってきました。
今回、読書会の一環として、従前の学会の蓄積を振りかえるとともに、それらに拠りつつ、分野の若手研究者の研鑽・交流を図ることを目的に、『日本社会教育学会年報 (日本の社会教育)』の序論を読んでいくこととしました。
多様なテーマを扱いながら、学会の足跡を振り返るという趣旨に鑑み、あらためて広く会員のみなさまからの参加を募ることといたしました。参加ご希望の方は下記にご連絡ください。
連絡先:c-shigyo◎g.ecc.u-tokyo.ac.jp(執行宛。◎を変換ください)
¬¬
次回の講読文献
直近の会は、以下を予定しています。
① 碓井, 1973, 「社会教育の方法をめぐる一、二の問題」『日本の社会教育』17号p3-18.
② 小林, 1974, 「社会教育職員研究の現代的意義」『日本の社会教育』18号p3-22.
③藤田, 1975, 「わが国の学習権保障運動とヨーロッパ資本主義国の動向」『日本の社会教育』19号 p10-27.
直近の開催日
5月7日(土)15時~
※今後も順次年報の序論を読みます(70年代より前も、将来的に検討予定です)
運営の方針
① 1~2ヶ月程度の間隔で、オンラインで開催
② 毎回の講読は、論文1~3本程度
③ 時間は1時間半~2時間
④ 大学院生等の若手中心の会
参考:これまで扱った文献
・第1回:宮原誠一, 1990「社会教育の本質」「社会教育入門」『社会教育論』国土社.
・第2回:小川利夫, 1973, 「戦後『社会教育』論の批判的再検討」『社会教育と国民の学習権』勁草書房.
・第3回:松下圭一, 2003, 『社会教育の終焉[新版]』公人の友社.
・第4回:
① 編集委員会「労働者教育の展望」『労働者教育の展望』14号(1970)p.1-11.
② 吉田昇「社会教育法制の基本問題」『社会教育法の成立と展開』15号(1971)p.3-17.
③ 持田栄一「生涯教育論」『生涯教育の研究』16号(1972)p.3-26.
日独シンポジウム(12月12日(日)17時〜21時:Zoom開催)の案内
日独シンポジウム:子ども・若者支援における専門性の構築
─日本とドイツの「社会教育的支援」研究に基づいて─
Construction of Professionality in the field of Child and Youth Services
-- on the basis of Studies of "Social Pedagogical Support" in Japan and Germany–
<趣旨>
日本とドイツの子ども・若者支援について、比較検討しながら、課題を検討するシンポジウムです。とりわけドイツの場合、子ども・若者支援法において、27歳未満の子ども・若者の権利として支援が保障され、そのための専門職が位置づいています。この経緯とともに、近年の動向と課題、今後の展望について報告を受け検討します。
主な内容は、下記の通りです。
- 日本とドイツの子ども・若者支援(主にユースワーク、ユースソーシャルワーク)における専門的従事者の専門性をめぐる歴史と課題
- 子ども・若者支援関係団体の側での専門性、研修に関する議論と枠組み設定
以上に関する報告・議論を踏まえて、子ども・若者支援領域に関わる専門性の枠組み、養成・研修の取り組みと課題を整理します。
<日時> 2021年12月12日(日)17:00- 21:00 (German time 9:00-13:00)
<開催方法> Zoom開催:奈良教育大学から配信
<タイムテーブル>
17:00 – 17:10 開会挨拶
17:10 – 17:40 報告:生田周二(奈良教育大学)
子ども・若者支援の日本の歴史と現状─専門性をめぐる研究を中心に─
17:40 – 18:10 報告:ヴェルナー・トーレ(Werner Thole:ドルトムント大学)
ドイツにおけるユースワーク─歴史、権利および目標、課題、施設、活動領域について─(Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland. Hinweise zur Geschichte, zum Recht sowie zu Zielen, Aufgaben, Einrichtungen und Arbeitsbereichen)
18:10 – 18:35 報告:ユリアン・ゼーマー(Julian Sehmer:応用科学芸術大学HAWKホルツマイデン)
子ども・ユースワークの支援者─養成・資格、専門性と専門職化(Das Personal der Kinder- und Jugendarbeit. Ausbildung und Qualifizierung, Professionalität und Professionalisierung)
18:35 – 18:50 休憩
18:50 – 19:15 報告:竹田明子(京都市ユースサービス協会)
ユースワークの日本の現状とユースワーカーの組織化
19:15 – 19:40 報告:谷口仁史(スチューデント・サポート・フェイス)
若者(就労)支援に関わる従事者の専門性の日本の現状
19:40 – 20:50 議論
20:50 – 21:00 まとめ・閉会挨拶
<言語>ドイツ語、日本語の通訳付き
<参加申込> 氏名、所属、メールアドレスを記載の上、以下のアドレスにご連絡下さい。後ほど、ミーティングID、パスワードを送付します。(締切:12月10日(金)12時)
子ども・若者支援専門職養成研究所:<ipty2014◎gmail.com> ※◎を@に変更してください
私たちのプロジェクトは、2013年以降、家庭と学校に並ぶ社会や職業生活への移行と自立を支援する「第三の領域」としての子ども・若者支援の枠組み、「社会教育的アプローチ」の位置づけ、専門性の確立に向け、4つの領域(原理論・比較研究領域、支援論・方法論研究領域、子ども領域、若者領域)に分かれて共同研究しています。
今回のワークショップが日本の子ども・若者支援のさらなる発展の機会となることを願っています。
 シンポジウム「子ども・若者支援研究のこれまでと今後の展開」
シンポジウム「子ども・若者支援研究のこれまでと今後の展開」
◎案内:子ども・若者支援専門職養成研究所 シンポジウム「子ども・若者支援研究のこれまでと今後の展開」(3月6日(土)13時〜17時:Zoom開催)
下記の通り、<シンポジウム「子ども・若者支援研究のこれまでと今後の展開」>を実施します。
※ 参加希望の方は、事前に申込をお願いします(締切:3月4日(木))。メールにより、ZoomのID・パスコードを送付します。
申込先:子ども・若者支援専門職養成研究所 <ipty2014◎gmail.com> ※◎を@に変えてください
記載事項:氏名、所属、e-mail、電話番号
<シンポジウム「子ども・若者支援研究のこれまでと今後の展開」(Zoom開催)>
日時:3月6日(土)13時から
主な内容:
13:00-13:10 趣旨説明など
13:10-14:30 子ども・若者支援のパラダイムデザイン─"第三の領域" と専門性の構築に向けて─
報告:生田周二(奈良教育大学教授)
コメンテーター:山本耕平(若年協同実践全国フォーラム:JYC共同代表、仏教大学教授)
14:30-14:50 支援論・方法論領域:サンプル版をベースにしたセミナーの実施報告
報告:櫻井惠子:奈良教育大学
15:00-16:50 子ども領域、若者領域の報告と検討
15:00~15:30 子ども領域
報告:川野麻衣子:北摂こども文化協会、井上大樹:札幌学院大学、
15:30~16:00 若者領域
報告:水野篤夫:京都市ユースサービス協会
16:00-16:50 グループセッションを含めた全体討議
16:50-17:00 まとめ
─科学研究費補助金(基盤研究B)「子ども・若者支援における専門性の構築─「社会教育的支援」の比較研究を踏まえて─」(研究代表者:生田周二)の一環─
 【開催案内】日本社会教育学会編『日本の社会教育第64集「学習の自由」と社会教育』合評会(オンライン開催)
【開催案内】日本社会教育学会編『日本の社会教育第64集「学習の自由」と社会教育』合評会(オンライン開催)
日本社会教育学会編『日本の社会教育第64集「学習の自由」社会教育』合評会(オンライン開催)のお知らせ
日本社会教育学会の3年間にわたるプロジェクト研究「『学習の自由』と社会教育」をもとに、年報第64集『「学習の自由」と社会教育』が、2020年9月30日に東洋館出版社から刊行されました。「九条俳句訴訟」を軸に、「学習の自由」や「学習権」等、さまざまな視点からまとめられた今回の年報について、下記要領で合評会を企画しました。
なお、当初は、九条俳句不掲載事件の発生したさいたま市内での開催を予定しておりましたが、おりからの新型コロナウィルスの感染拡大、さらなる緊急事態宣言の発出という展開をふまえ、全面的にオンライン(Zoom)で開催することに致しました。
参加ご希望の方は、お名前と所属を明記して、2021年2月1日(月)までに下記申込先にメールでお申し込みください。折り返しZOOMのURL等をお送りいたします。
日時:2021年2月7日(日)午後1時30分から午後5時
第1部 本書の全体的な成果・課題をめぐって(1時30分から2時45分)
司会 佐藤一子さん(東京大学名誉教授)
報告者:久保田和志さん(九条俳句訴訟弁護団事務局長の立場から)
勝野正章さん(東京大学、教育行政・教育法学の立場から)
長澤成次さん(放送大学千葉学習センター、編集委員長の立場から)
*報告一人20分程度。その後、質疑・討論。
<休憩15分>
第2部 本年報の「学習権」論が提起したもの(3時から5時)
司会 安藤聡彦さん(埼玉大学)
報告者:石川智士さん(九条俳句訴訟弁護団)
姉崎洋一さん(札幌大学女子短期大学部・北海道大学名誉教授)
*報告 一人20分程度。その後、質疑・討論。
総括コメント:朝岡幸彦さん(東京農工大学)
*お申し込み・問い合わせ先:
長澤成次:nagasawa◎faculty.chiba-u.jp ※◎を@に変えてください。
 【開催案内】学術変革領域研究「生涯学」キックオフミーティング+公募研究説明会
【開催案内】学術変革領域研究「生涯学」キックオフミーティング+公募研究説明会
学術変革領域研究「生涯学」キックオフミーティング+公募研究説明会趣旨
令和二年度科学研究費助成事業「学術変革領域研究(A)」に、研究領域 「生涯学の創出-超高齢社会における発達・加齢観の刷新(略称「生涯学」)」 (領域代表者:月浦崇、研究期間:令和二年~六年度)が採択されました。 本領域は、従来の「成長から衰退へ」という固定的な発達・加齢観を刷新し、人間の生涯における変化を、多様な成長と変容を繰り返す生涯発達のプロセスとして明示することを目的としています。行動解析による認知心理学的研究、脳活動測定による生理心理学的研究、精神疾患や認知症に関する臨床心理学的研究、社会調査をもとにした社会学的研究、フィールド調査をもとにした文化人類学的研究、そしてそれらの基礎研究の成果を社会実装するための教育学的研究を有機的に連携させ、基礎から応用までの展開を進める多元的な人間研究を実施します。つきましては、下記の要領で、当該領域のキックオフミーティングを開催いたします。
また、2021年1月に2021年度からの公募研究班の募集が開始されますので、キックオフミーティング内にて公募研究の説明を行います。公募研究では、各計画班に関連する研究に加えて、「生涯学」のコンセプトに関わる境界領域の研究も公募する予定ですので、多くの方の積極的な参加をお待ちしております。
参加には事前登録が必要です。参加を希望する方は、下記のウェブサイトより登録をお願いします。
日時: 2021年1月23日(土)13:00-14:30
実施形式:Zoomによるオンライン
事前申し込みサイト:https://ws.formzu.net/dist/S55235400/
言語: 日本語
参加費:無料
問い合わせ:lifelongsciences◎gmail.com ※◎を@に変えてください。
領域ホームページ:https://www.lifelong-sci.jinkan.kyoto-u.ac.jp/
主催:科研費学術変革領域研究「生涯学の創出-超高齢社会における発達・加齢観の刷新」
※ 石井山竜平会員からの情報提供です。
Zoom版ラウンドテーブル「子ども・若者支援において“社会教育的支援”をどう位置づけるか(2)」の開催について……2020年5月24日(日)
学会六月集会(宇都宮大学)で予定していたラウンドテーブル(5月24日(日)午後)が中止となったため、Zoomを使って実施します。なお、Zoomについては、セキュリティの脆弱性が心配されるため、下記の◎付記1に記載の通り参加登録制で行います。
◎日時:2020年5月24日(日)13時30分〜16時
①テーマ:子ども・若者支援において「社会教育的支援」をどう位置づけるか(2)
②コーディネーター:生田周二・奈良教育大学
③報告者:
大村惠・愛知教育大学
津富宏・静岡県立大学
櫻井裕子・奈良教育大学
④内容:
科研による研究プロジェクトで2020年3月末に作成した『子ども・若者支援専門職養成ガイドブック─共通基礎─』(sample版)(子ども・若者支援専門職養成研究所編)について報告を踏まえて議論します。ガイドブックは、子ども・若者支援に関わる人たちの「共通基礎レベル」の知識と方法論、大切にすべき価値に関する養成・研修のための試行版です。 合評会的に議論したいと思います。
なお、ガイドブックの構成は以下の通りです(全87頁:付記2参照)。
はじめに……ガイドブックの編集目的と「子ども・若者支援の従事者の専門性」概説
Ⅰ 子ども・若者支援の課題把握
1 子ども・若者をめぐる歴史・子どもの権利・法・文化・取り組みなどの概要の理解
2 子ども・若者支援の基礎概念(自尊感情、対話、居場所、自立)の理解と教育的・福祉的対応の理解
3 子ども・若者支援をめぐる現代的課題の理解
4 海外の動向を踏まえた、“第三の領域”としての子ども・若者支援の理解
5 子ども・若者支援の福祉的側面の理解
B-1 子ども・若者支援における医療的支援─発達障害、精神疾患とその支援─
Ⅱ 支援の方法論の把握・活用
1 子ども・若者と出会い、向き合う(居場所と対話・自尊感情に関する理解を踏まえた対応)
2 集団・コミュニティ形成への支援─主体性を尊重する支援方法─
3 リフレクションの展開、ケース記録などの作成・整理
B-1 心理アセスメント、カウンセリング、心理療法(サイコセラピー)の技法
B-2 困難を抱える若者に対する自立までの継続的な支援
B-3 家族支援、ペアレントトレーニング、オープンダイアログ
Ⅲ 社会性・寛容性、連携力
1 関係者、支援者や学校などの機関との連携やネットワークの構築と活用
2 児童虐待等の早期発見、ならびに児童相談所等の関係機関と連携した対応
3 事例研究「NPO法人いまから」の実践に学ぶ
⑤プログラム(予定)
13時30分〜40分 趣旨説明
13時40分〜14時05分 報告:櫻井裕子 ……心理的側面を踏まえ子どもとの関係性を探る
14時05分〜14時15分 質疑(1)
14時15分〜14時40分 報告:津富宏 ……若者の自立を問い直しつつ連携のあり方を探る
14時40分〜14時50分 質疑(2)
休憩10分
15時00分〜15時25分 報告:大村恵 ……人格形成に視点を当て、教育的・集団的アプローチを探る
15時25分〜15時35分 質疑(3)
15時35分〜16時 全体討議
◎付記1……参加希望の方は、生田までメール( ikuta@cc.nara-edu.ac.jp )で、氏名・所属を記載し、5月22日(金)までに連絡をください。ZoomのミーティングIDとパスワードを送付します。ミーティングIDと一緒に記載されるURLをクリックしていただけると、IDとパスワードを入力する画面となります。初めての方は、アプリケーションをダウンロードするなどの手間は必要ありません。よろしくお願いいたします。
◎付記2……ラウンドテーブルで扱う『子ども・若者支援専門職養成ガイドブック─共通基礎─』(sample版)がダウンロードできるURLは、ミーティングIDとパスワードを送付する際に連絡します。
以上、よろしくお願いいたします。
「障害者と社会教育」研究会開催のお知らせ
2019年度日本社会教育学会若手会員の萌芽的研究「多様な実践を包摂する『障害者社会教育』の論理構築に関する研究」の一貫として、以下の研究会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
テーマ:「障害者と社会教育」をめぐる実践動向―2000年代以降の展開に着目して―
日時:2020年2月1日(土) 13:00~16:00
会場:神戸大学 人間発達環境学研究科 A347教室(正門正面の建物の3F)
〒657-0013 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目11
司会:佐藤健吾(東洋大学大学院)・竹井沙織(名古屋大学大学院)
報告:井上太一(神戸大学大学院)・津田英二(神戸大学)「神戸大学の取り組み:学ぶ楽しみ発見プログラム、のびやかスペースあーち、カフェアゴラ」
松室朝香(京都女子大学大学院)・岩槻知也(京都女子大学)「京都市青少年活動センターにおける余暇活動支援事業」
島本優子(コーヒーハウススタッフ)・末光翔(東京大学大学院)「東京都国立市公民館コーヒーハウスの実践」
参加申込:1/27(月)までに下記URLよりお申し込みください
https://forms.gle/5ZTmkJxDMAPM7P5v7
詳細は開催要項(PDF)をご参照ください。→「障害者と社会教育」研究会開催要項(PDF)
<事務局員の勤務について>
事務局は事務局は事務局は祝祭日を除く(月)・(木) 10:00~16:00 リモートワークのため、電話受付はしておりません。お問合せ等はメールにてご連絡ください。
【事務局メール: jssace.office@gmail.com】
ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【会費振込先】今年度(2026年度)が2025年9月から始まっています。会費納入状況は各自個人画面で確認の上、会費未納分と今年度分の会費の振込みをお願いいたします。尚、2026年度会費減額申請は受付終了しています。2027年度については2026年7/1(水)~2027年8/15(土)です。減額希望の会員は期間内に<会費減額申請システム>から申請し、承認の連絡が来次第、会費の納入をしてください。(10月開催予定の理事会で承認後ご連絡いたします。)
ゆうちょ銀行 振替口座 00150-1-87773
他金融機関からの振込用口座番号:〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座0087773
*口座振替ご希望の方 個人ページにアクセスした後、下方<会則・文書等>にあります「預金口座振替依頼書」に必要事項を入力後プリントアウトし、押印したものを学会事務局までご郵送ください。今年度(2026年度)は2025年10月15日必着で〆切りました。
*領収書が必要な方 会費等の領収書が必要な方は、メールにて領収書の宛名・送付先をお知らせください。
◎会員の方は各自、登録メールアドレスの確認をお願いいたします。
「六月集会プログラム」「学会からのお知らせ」「研究大会プログラム」はネット配信のみになります。
〒189-0012
東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail:jssace.office◎gmail.com
(◎を@に変えてください)
(祝祭日除く月・木曜日 10:30-16:30 リモートワーク中)
Tel:090-5782-1848 ※現在電話受付停止中