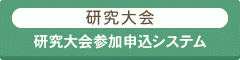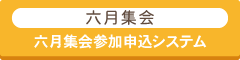会員企画のお知らせ
シンポジウム「子ども・若者の目線で社会のあり方を考えよう」のご案内
一般社団法人日本社会教育士会
2022年度シンポジウム「子ども・若者の目線で社会のあり方を考えよう」開催案内
子ども・若者が生き難さを抱え様々な困難に直面していると報じられて
います。
こうした状況に対して社会教育は、どのようなことに取り組んでいけば
よいのでしょうか。
今年度のシンポジウムでは、全国各地で子ども若者のために実践に取り
組んでいる方々からその実践を報告していただき、地域の社会教育実践
についてや社会教育士、社会教育職員のあり方を考え合うシンポジウム
を開催します。
ぜひご参加くださいますようお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日時:2023年2月17日(金)19時30分から21時30分
開催方法:オンライン
パネリスト:小野寺玲さん(福井スコーレ)
渋谷幸靖さん(特定非営利法人陽和)
ファシリテーター:大村惠さん(愛知教育大学・日本社会教育士会理事)
参加費 :会員無料、一般 1000円、学生500円
申込 :一般社団法人日本社会教育士会 | Peatix (http://ptix.at/uuvhT9)
詳細 :当会ホームページ (https://onl.la/nYEHY7s)をご覧ください
※お申し込みの皆様には、後日、Zoomの接続情報をお知らせいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご案内「東アジアの友情形成と草の根の学び」
日本社会教育学会 関係各位
会員の阿知良と申します。
関心のある方にご参加いただけたらうれしく思い、この場を借りてご案内申し上げます。
「東アジアの友情形成と草の根の学び」
趣旨 ウクライナ情勢・東アジア情勢を前に、軍拡が世論を覆っています。
しかし、草の根の学びの中には、軋轢・対立は対話によって解決の道を探ることができると確信を掴み実践してきた蓄積があります。
北海道・朱鞠内では国境を越えた若者たちが集い、アジア太平洋戦争中の強制労働犠牲者の遺骨の発掘を通じて友情を形成してきました。
その舞台となった笹の墓標展示館が雪で倒壊しましたが、その再生活動を次の世代が中心になって行っています。
再生活動の事務局を担う金英鉉さんに学び、現在の情勢下での草の根の対話と学びの価値を再検討したいと思います。
■日時:2月4日(土)19:00~20:30
■場所:zoom 定員30名 無料
■報告者:金英鉉さん(笹の墓標再生実行委員会事務局)
■笹の墓標展示館の活動についての参考HP https://www.sasanobohyo.com/
■参加申し込み:締め切り2月3日(金)18:00 achiray◎mmm.muroran-it.ac.jp(阿知良洋平、◎を@に変更)まで、氏名、所属、メールアドレスを連絡ください。当日の朝までにzoomのアドレスを送ります。
■世話人 阿知良洋平、栗山究、浪指拓央、萩原達也
■問い合わせ先:阿知良洋平 achiray◎mmm.muroran-it.ac.jp ※◎を@に変更
第1回鹿児島大学リカレント教育シンポジウムのお知らせ
日本社会教育学会関係各位
この度、社会人向けの教育プログラムの開発とその実施体制の確立を目的に、「第1回 鹿児島大学リカレント教育シンポジウム」を下記日程の通り開催いたします。
ご多忙中大変恐縮ではございますが、貴部局の教職員・学生へのご参加およびご周知方、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
記
【日 時】 令和4年11月5日(土)13:00~16:00
【開催場所】 郡元キャンパス 農・獣医学部共通教育棟101
【参加費】 無料
【申込方法】 鹿児島大学高等教育研究開発センター
生涯学習部門HPよりお申込み下さい。
https://www.life.kagoshima-u.ac.jp/
※申込締切:11月1日(火)16時
⇒締切の記載は1日となっておりますが、11月4日に延長することになりました。(追記)
【問合せ先】 高等教育研究開発センター・生涯学習部門 中村・水谷
099-285-7122(内戦7122)
どなたでも参加いただけるシンポジウムです。
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
なお詳細は、下記の添付ファイルを参照ください。
全国障がい者生涯学習支援研究会のご案内
日本社会教育学会 会員の皆様
下記の通り、研究集会の案内がありましたので、転送いたします。
********
会員の寺谷直輝(@愛知)と申します。
全国障がい者生涯学習支援研究会が主催している研究集会の案内を情報共有いたします。
興味のある方は、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。
日 時:2022年12月4日(日) 10:00〜16:00
(開場 9:30)
場 所:愛知県立大学サテライトキャンパス(ウインクあいち15階)
内 容:課題研究「障害者生涯学習政策5年間の検証」
研究発表
定 員:50名(申し込み先着順) ※定員となり次第、受付終了となります。
参加費:会員4,000円(一般5000円)
★研究誌7号代と送料を含みます。
参加費は当日受付にてお支払いください。
参加申込:以下のフォームに記入・送信をお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQsCh__SST7Gxt200QCvAn3mIvh-1UeuZK4kDr46G6Q_EiQ/viewform
HPはコチラです!
https://sss-kenkyu.jimdofree.com/
ー---------------------
<プログラム>
(日時)2022年12月4日(日)10:00-16:30
(開場 9:30)
(場所)愛知県立大学サテライトキャンパス(ウインクあいち15階)
司会:水野和代(日本福祉大学講師)
10:00〜10:10 あいさつ
田中良三(愛知県立大学名誉教授)
<課題研究>
(テーマ)障害者生涯学習政策5年間の検証
司会:京 俊輔(島根大学准教授)
小林洋司(日本福祉大学准教授)
10:10〜11:30【前半】発表20分+質疑10分
①文部科学省の立場から
鈴木規子(文部科学省障害者学習支援室室長)
②政策支援の立場から
津田英二(神戸大学教授)
③実践研究委託事業から
田中良三(愛知県立大学名誉教授)
11:30〜12:20 <昼食・休憩>
12:20〜12:50 総 会
議長:寺谷直輝(大同大学他非常勤講師)
12:50〜14:50【後半】発表20分+質疑10分/全体討論50分・まとめ10分
④障害者生涯学習研究から
小林 繁(明治大学教授)
⑤社会教育・生涯学習研究の立場から
辻 浩(名古屋大学教授)
★全体討論・まとめ
<研究発表> 発表20分+質疑10分
司会:田中隆人(立命館大学大学院博士後期課程)
15:00~15:30 「余暇活動と学び」
田中克也(地域活動支援センターdeco boko BLUES代表)
15:30~16:00 「地域における障害者の生涯学習支援の構築-春日井市における民間と行政の連携・協働による体制づくり-」
志村美和(春日井子どもサポートKIDS COLOR代表)
なお、詳細については、下記の添付資料もあわせて参照ください。
国立女性教育会館(ヌエック)・ 男女共同参画センターに関する 緊急連続学習会のお知らせ
日本社会教育学会 会員各位
政府は本年6月に「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022(女性版骨太の方針2022)」を発表しました。
その中で、国立女性教育会館(ヌエック)の所管を文部科学省から内閣府に移管することが打ち出されました。
また、各地の男女共同参画センターについて、その機能の強化・充実をはかるとともに、それらを「束ねる」拠点としてヌエックの機能を強化する、との内容も盛り込まれました。社会教育の研究・実践にかかわってきた者として私たちは、この方針をどのように受けとめればよいのでしょうか。これを考えるにあたり、ヌエックや男女共同参画センター等について、これまでの経緯や現状を知り、今後の役割について議論する場を、急きょ、設けることにしました。皆さんのご参加をお待ちしております。
第1回 2022年10月10日 19時30分~21時30分 国立女性教育会館(ヌエック)とは
第2回 2022年11月8日 19時30分~21時30分 男女共同参画センターの学習・教育事業の現状と課題
第3回 2022年11月28日 19時30分~21時30分 女性関連施設/社会教育施設等の担い手の現状と課題を考える
なお、申し込み先・連絡先などの詳細に関しては、下記のファイルを参照ください。
<事務局員の勤務について>
事務局は事務局は事務局は祝祭日を除く(月)・(木) 10:00~16:00 リモートワークのため、電話受付はしておりません。お問合せ等はメールにてご連絡ください。
【事務局メール: jssace.office@gmail.com】
ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【会費振込先】今年度(2026年度)が2025年9月から始まっています。会費納入状況は各自個人画面で確認の上、会費未納分と今年度分の会費の振込みをお願いいたします。尚、2026年度会費減額申請は受付終了しています。2027年度については2026年7/1(水)~2027年8/15(土)です。減額希望の会員は期間内に<会費減額申請システム>から申請し、承認の連絡が来次第、会費の納入をしてください。(10月開催予定の理事会で承認後ご連絡いたします。)
ゆうちょ銀行 振替口座 00150-1-87773
他金融機関からの振込用口座番号:〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座0087773
*口座振替ご希望の方 個人ページにアクセスした後、下方<会則・文書等>にあります「預金口座振替依頼書」に必要事項を入力後プリントアウトし、押印したものを学会事務局までご郵送ください。今年度(2026年度)は2025年10月15日必着で〆切りました。
*領収書が必要な方 会費等の領収書が必要な方は、メールにて領収書の宛名・送付先をお知らせください。
◎会員の方は各自、登録メールアドレスの確認をお願いいたします。
「六月集会プログラム」「学会からのお知らせ」「研究大会プログラム」はネット配信のみになります。
〒189-0012
東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail:jssace.office◎gmail.com
(◎を@に変えてください)
(祝祭日除く月・木曜日 10:30-16:30 リモートワーク中)
Tel:090-5782-1848 ※現在電話受付停止中