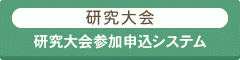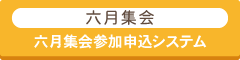最新情報
『社会教育学研究』第62巻第2号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第62巻第2号(2027年1月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。
投稿にあたっては、『社会教育学研究』第61巻第2号巻末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】
2026年5月1日(金)~2026 年5月31日(日)
【原稿種別について】
<一般>(自由テーマによる論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・ 研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果を社会教育学の視点からまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
・なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
<特集>(以下の特集テーマに基づいた論文)
・「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・テーマ:多文化・多民族共生を目指す社会教育の挑戦
・趣旨: 2025年7月の参議院選挙に現れたように、日本社会で排外主義が広まっている中、いま一度多文化・多民族共生から社会教育を捉えなおしていくことの必要性や重要性が高まってきている。本特集では、社会教育における多文化・多民族共生を多様な観点から考察する論文を募集する。
第一に、社会教育における多文化・多民族共生にかかわる諸課題について募集する。1995年の日本社会教育学会年報『多文化・民族共生社会と生涯学習』以降、多文化・多民族共生をめぐる制度や社会的状況は変わってきている。クルド難民など新たな対象に関する課題や地域間格差の問題など、今までの成果を踏まえた新しい実践や研究を幅広く募集する。
第二に、多文化・多民族共生の観点からの社会教育の「再」定立にかかわる理論的枠組みや課題につながる考察を募集する。脱植民地主義の位置づけやフォーマル教育との関係、先住民族に対する和解の問題など、いまだに課題として残されている分野や領域に対して様々な観点からの論考を期待する。
【査読基準の公開】
・『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の留意点】
・ 本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。所属機関に研究倫理審査規程がある場合は、必ず所属機関の規程に従ってください。また、所属機関の研究倫理審査を経ている場合は、その旨を本文中に記載ください。
・また、投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。特に連続投稿(投稿規程の3)、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
・近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
『社会教育学研究』第62巻第1号における論文電子投稿システム稼働のお知らせ
日本社会教育学会 会員各位
『社会教育学研究』第62巻第1号(2026年5月刊行予定)における論文電子投稿システムを稼働致しました。
論文投稿を検討されている方は、下記の要項をよく読んだ上で、学会HPにログインし、画面左の列の茶色のボタン(社会教育学研究論文投稿システム)から入ってください。ページの下部に投稿フォームがありますので、必要事項を記入の上、投稿するようにして下さい。
【投稿原稿受付期間】
2025年11月1日(土)~2025 年11月30日(日)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、年間2回の刊行です。今回は、第1号の募集で【一般論文】を受け付けます(第2号の募集は、2026年5月1日〜5月31日を予定)。
【原稿種別について】
・『社会教育学研究』では「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
・研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
・なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
【査読基準の公開】
・『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の留意点】
・本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。所属機関に研究倫理審査規程がある場合は、必ず所属機関の規程に従ってください。また、所属機関の研究倫理審査を経ている場合は、その旨を本文中に記載ください。
・また、投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。特に連続投稿(投稿規程の3)、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
・近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
口座引き落としに関して
日本社会教育学会 各位
これまで口座振替の場合は希望者に書類を郵送して、必要事項を記入後押印して返送してもらっておりましたが、今年から電子ファイル版の提供が開始されました。
つきましては、会費の引落口座を変更・新規ご希望の方は、下記の通り、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
①学会事務局にメールを入れる
②学会HPにログインをする
③個人会員ページ内、左列「会則・文章等」の中の最下部のファイル(預金口座振替依頼書)を各自ダウンロードし必要事項記載後プリントアウトして押印したものを学会事務局宛に郵送する
上記を含め、引落し口座の変更・取止め、または新規ご希望の方の受付については、2025年9月末日までに事務局宛ご連絡頂くように通信にて告知しておりましたが、こちらを10月15日締め切りに延長を致します。
なお、次回2026年度分引落は、2025年12月20日(予定)ですので、各自、残高をご確認ください。以上、宜しくお願いします。
日本社会教育学会 事務局
『社会教育学研究』第62巻第1号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第62巻第1号への投稿原稿の募集
『社会教育学研究』第62巻第1号(2026年6月刊行予定)への投稿原稿を募集いたします。
投稿にあたっては、『社会教育学研究』第61巻1号末、及び学会Webページに掲載されている倫理宣言・編集規程・投稿規程・執筆要領を確認いただいた上で、本学会の会員専用サイトから「『社会教育学研究』論文電子投稿システム」を用いて、下記の受付期間の間にご投稿ください。
【投稿原稿受付期間】2025年11月1日(土)~2025年11月30日(日)
【年間2回刊行について】
『社会教育学研究』は、年間2回の刊行です。今回は、第1号の募集で【一般論文】を受け付けます(第2号の募集は、2026年5月1日〜5月31日を予定)。
【原稿種別について】
l 『社会教育学研究』では、「研究論文」「研究ノート」「実践報告」の3種類の原稿を募集しています。
l 研究論文においては研究上の独創性や学術的貢献の高さが、研究ノートにおいては各主題に関して適切なアプローチがなされていることが、実践報告は単なる実践紹介でなく実践の内容や成果をまとめることが期待されています。投稿の内容に応じて適切な原稿種を選択して投稿いただくようお願いします。詳しくは、編集規程・投稿規程・執筆要領をご参照ください。
l なお、投稿後の原稿種の変更は認めておりません。また、査読の過程において原稿種の変更を求めることはありません。投稿前に原稿種別について慎重にご検討いただきますようお願いします。
【査読基準の公開】
『社会教育学研究』では、Webページにて「査読基準」を公開しています。投稿前にご参照ください。
【その他の注意点】
l 本学会の研究倫理宣言を遵守しない原稿については、査読の対象になりません。投稿前に倫理宣言に目を通していただき、投稿する原稿の内容や研究方法に問題がないか、ご自身でチェックをいただくようお願いします。なお、倫理的配慮が必要な内容であり、所属機関で倫理研究審査を受けている場合は、その旨を本文中に示していただくようにお願いいたします。
l 投稿規程、執筆要領を遵守していない論文も受理することはできません。ご注意ください。前号に採用された者の連続投稿はできませんが、特集テーマに関する論文等はこの限りではありません(投稿規程の3)。また、二重投稿や自己盗用(投稿規程の5)、重複投稿(各号で投稿できるのは単著、共著問わず1人1本です)にならないよう、事前のチェックをお願いします。
l 近年、規定字数を超過した原稿が目立ちます。Wordのカウント機能を用いるなどして、事前に入念に確認をしてからご投稿ください。
(『社会教育学研究』編集委員会)
2026年度会費減額申請システムの稼働について
日本社会教育学会 会員各位
2026年度(2025年9月~2026年8月まで)の「会費減額制度」の申請を受け付けます。本制度のご利用を希望される会員は、下記の要領にてフォームより申請してください。以前に「減額」を継続と申請された方はあらためて申請する必要はございません。
【対象】
・学生(大学院生を含む)、または常勤職にない会員等(※本制度概要4参照)
【申請期間】
・2025年7月1日(火)~2025年8月15日(金)
【申請方法】
・下記フォームより申請
《会費減額制度の概要》
1.本制度は、経済的な制約により学会加入が困難になる状況を少しでも改善することを目的として、個人への経済支援を行うものである。
2.本学会は、本人からの申請にもとづき年会費の減額を行う。
3.一年を単位として、年会費1万円を6,000円とする(4,000円の減額)。
4.申請者は、会費を払う年度において、大学院生または常勤職にない会員等とする。本制度の主旨に則り、学術振興会の特別研究員、および、それに準ずる身分の者等、一定金額の収入のある者は申請できない。なお、申請者は、減額を受けようとする年度の前年度までの会費滞納のないことを要する(新規の入会者を除く)。
5.申請者は、学会HPの個人ページにある<会費減額申請システム>から申し込む。
6.申請受付期間は、毎年7月1日〜8月15日とする(期限厳守)。新入会者で減額希望の場合は入会届とともに減額申請書に必要事項を記入し提出することができる。(減額申請書を提出する場合は、会費の振込は6,000円とする。)
7.本学会は、新年度開始後の理事会(10月開催予定)において、申請者リストを回覧し、承認を行う。その後、事務局より承認の可否をメールにて申請者に通知する。
8.申請者は、申請の承認可否の結果を受けた後に当該年度の年会費を支払うものとする。
9.減額制度は一年ごとに適用する。申請は年度ごとに受けつける。但し、継続申請した場合を除く。継続確認は事務局までお問合せください。
<事務局員の勤務について>
事務局は事務局は事務局は祝祭日を除く(月)・(木) 10:00~16:00 リモートワークのため、電話受付はしておりません。お問合せ等はメールにてご連絡ください。
【事務局メール: jssace.office@gmail.com】
ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【会費振込先】今年度(2026年度)が2025年9月から始まっています。会費納入状況は各自個人画面で確認の上、会費未納分と今年度分の会費の振込みをお願いいたします。尚、2026年度会費減額申請は受付終了しています。2027年度については2026年7/1(水)~2027年8/15(土)です。減額希望の会員は期間内に<会費減額申請システム>から申請し、承認の連絡が来次第、会費の納入をしてください。(10月開催予定の理事会で承認後ご連絡いたします。)
ゆうちょ銀行 振替口座 00150-1-87773
他金融機関からの振込用口座番号:〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座0087773
*口座振替ご希望の方 個人ページにアクセスした後、下方<会則・文書等>にあります「預金口座振替依頼書」に必要事項を入力後プリントアウトし、押印したものを学会事務局までご郵送ください。今年度(2026年度)は2025年10月15日必着で〆切りました。
*領収書が必要な方 会費等の領収書が必要な方は、メールにて領収書の宛名・送付先をお知らせください。
◎会員の方は各自、登録メールアドレスの確認をお願いいたします。
「六月集会プログラム」「学会からのお知らせ」「研究大会プログラム」はネット配信のみになります。
〒189-0012
東京都東村山市萩山町2-6-10-1F
E-mail:jssace.office◎gmail.com
(◎を@に変えてください)
(祝祭日除く月・木曜日 10:30-16:30 リモートワーク中)
Tel:090-5782-1848 ※現在電話受付停止中